2025年9月石破茂首相が辞任の意向を固め、日本の政局が一気に動き出しました。
次の総裁は誰になるのか?いつ決まるのか?—そんな声がネットやテレビで飛び交っていますよね。
この記事では次の自民党総裁候補として有力視される高市早苗、小泉進次郎、玉木雄一郎の特徴と支持層を徹底解説します。
さらに総裁選の仕組みや選挙方式の違い、今後の衆議院解散や再組閣の可能性まで、最新情報をもとにまとめました!
こんなことがわかります👇
- 総裁選はいつ、どうやって行われるのか
- 有力候補の強み・注目ポイント
- 今後の政局はどうなるのか
ぜひ最後までご覧ください。
なるほどね…
— しのぶレイド@猫と蝶💫 (@Hosc_Matm) September 7, 2025
小泉ジュニアが石破に引導を渡す演出ですか
これで次期総裁、総理は小泉ですね
茶番だね#ザイムの狗 #岸破ヒロシの専制
【速報】石破総理が辞任の意向固める 党の分断避ける狙いか 自民・閣僚経験者は「これが唯一の道だった」夕方から会見へ#Yahooニュースhttps://t.co/jcFhfYMNCg
次の総裁候補は誰?有力視される人物たち
石破茂首相が辞任の意向を固めたことで、次の総裁候補に誰がなるのか注目が集まっています。
現在名前が挙がっているのは高市早苗、小泉進次郎、玉木雄一郎などの面々です。
それぞれ異なる支持層とバックグラウンドを持ち、総裁選の展開によっては大きな政局転換が予想されます。
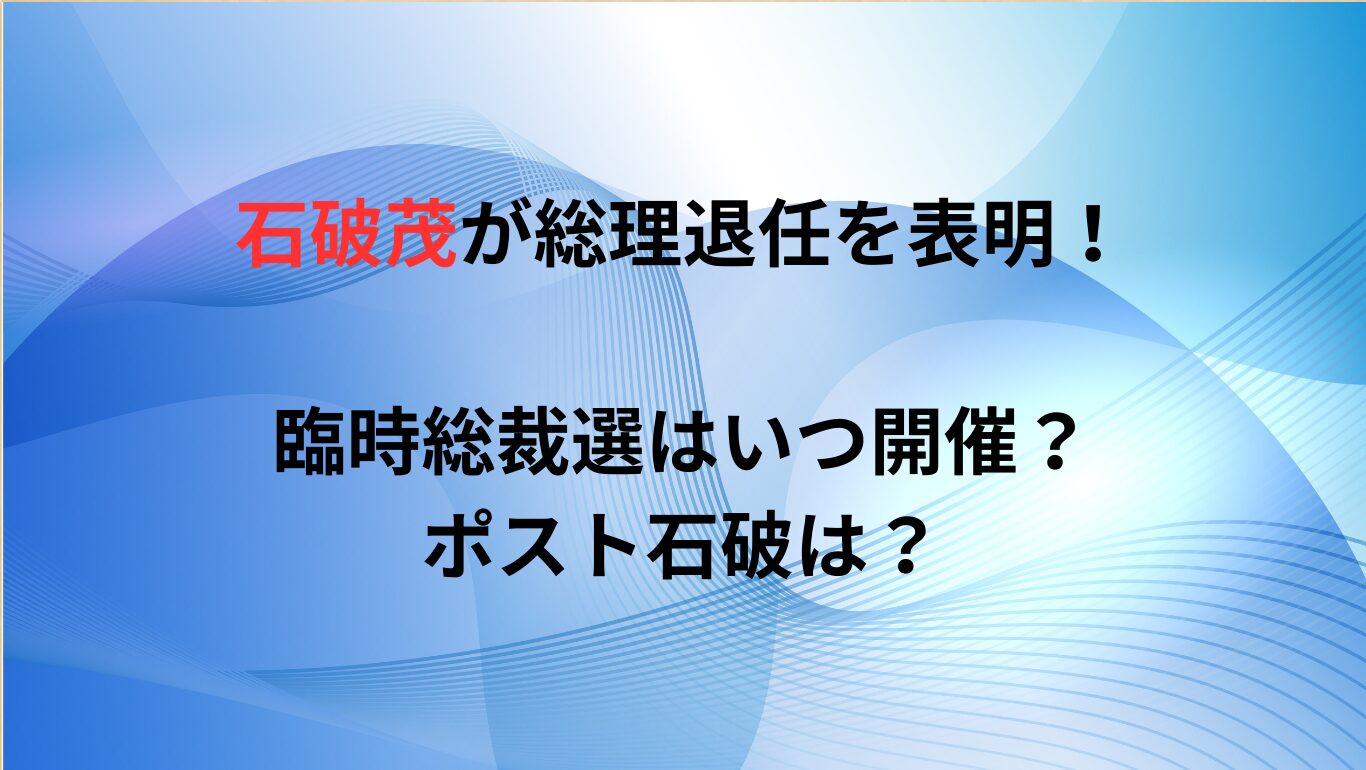
高市早苗|保守層と女性支持層からの圧倒的支持
高市早苗が有力候補とされる理由は、強固な保守層の支持と「女性初の総裁」への期待です。
自民党内でも右派色が強い政策を掲げ、特に安全保障や経済安全保障の分野では明確な方針を示してきました。
過去には経済安全保障担当相としても実績があり、保守層からの信頼は厚いです。
さらに女性初の自民党総裁・総理大臣という可能性が現実味を帯びており、女性支持層や無党派層からの注目も集まっています。
毎日新聞の世論調査では、高市早苗は14%の支持を集め、石破茂に次いで2位につけていました。
これは小泉進次郎(9%)や玉木雄一郎(6%)を上回る数字であり、党内外での存在感の高さを物語っています。
派閥の支援基盤こそ限定的ですが、岸田派や安倍派の再編の中で浮上する可能性もありますね。
今後の動き次第では、女性の総裁誕生という歴史的瞬間を目にするかもしれません。
石破辞任した後は高市早苗さんが来て欲しい
— のらえもん。 (@lJrvNPx4WQsyEoL) September 7, 2025
小泉進次郎はやめてくれて…… https://t.co/DL5CIZKzsZ
小泉進次郎|若年層の期待と改革イメージ
小泉進次郎が次の総裁候補として注目されるのは、若年層からの期待感と「改革派」としてのイメージが強いからです。
自民党の中でも珍しく、世襲のイメージを超えた独自の発信力があり、メディア対応やSNSでの存在感が抜群です。
過去には環境大臣として「プラスチックごみ削減」など環境問題に積極的に取り組み、若者や子育て世代に響く政策を打ち出してきました。
今回の内閣でも農林水産大臣として物価高対策や農業改革に取り組んでおり、世論調査でも9%の支持を集めています。
保守本流とは少し距離を置いた立ち位置が「しがらみのない改革派」として支持されやすく、特に無党派層・都市部の若い世代からの人気が高いです。
また小泉純一郎元首相を父に持つ「政治一家」としての知名度の高さも大きな武器になっていますね。
ただし党内での派閥支援が不透明なことや、「内容の薄さ」を指摘する声も根強く、総裁選で勝ち抜くには政策と組織力の両方が問われそうです。
今朝の毎日の記事。これを読んで辞任を表明するなら、総裁選に出馬か。自民支持者だけでなく国民全体でも石破氏がもっとも首相にふさわしいという世論。鈴木宗男氏が言う通りだ。
— Norichika Horie (@NorichikaHorie) September 7, 2025
読む政治:石破、高市、小泉、玉木氏……「ポスト石破」の支持層と支持理由は? | 毎日新聞 https://t.co/4yz1ASlbzh
玉木雄一郎|野党出身でも注目される理由とは?
玉木雄一郎が次の総裁候補として注目を集めているのは、野党出身ながらも現実路線と調整力の高さが評価されているからです。
国民民主党の代表として、与党との協議に積極的な姿勢を示してきた玉木雄一郎は、「対立より協調」を重視するスタンスで知られています。
そのため自民党内の保守中道層や無党派層からも「話が通じる野党政治家」として名前が挙がるようになりました。
また政策面では経済再生や教育改革に強い関心を持ち、現場主義で課題に取り組む姿勢も評価されています。
毎日新聞の世論調査では6%の支持を獲得しており、自民党以外の人物としては異例の高評価です。
さらに石破茂政権下での「野党との協議型政治」によって、与党内に「玉木雄一郎との連携ならやれる」との空気が広がってきたことも大きいですね。
もちろん現時点では正式な自民党員ではないため総裁選出馬にはハードルがありますが、与党入りの噂も根強く、今後の動向は要注目です。
石破茂首相が辞任表明!辞任までの経緯と背景
石破茂首相が辞任を表明した背景には、参議院選挙の大敗と党内の強まる圧力がありました。
このタイミングでの辞任表明は、総裁選の前倒しを求める声が広がる中、自民党の分裂を防ぐ狙いもあったとされています。
参院選敗北と党内の圧力
石破茂首相が辞任を決断する直接のきっかけとなったのは、2025年7月に行われた参議院選挙での惨敗です。
自民・公明の与党で過半数を下回る結果となり、自民党内では「3連敗(衆院選、都議選、参院選)」として責任を問う声が噴出しました。
さらに、麻生太郎最高顧問や菅義偉副総裁といった大物政治家たちも、早期の辞任を促す発言を相次いで行いました。
自民党内では両院議員総会の開催を求める署名が集まり、「党員の総意として石破では選挙を戦えない」とのムードが広がっていたのです。
また両院議員総会の場では「党の団結を維持できない」「執行部のままでは次の選挙に勝てない」といった意見が続出し、四役も辞意を示す状況に。
石破茂首相自身も「しかるべき時にきちんと決断する」と語っていたように、状況の深刻さは認識していたようです。
結果として、8日の総裁選前倒しの決定を待たず、7日に辞任の意向を固めるに至りました。
辞任を決断した理由と会見内容の要旨
石破茂首相が辞任を決断したのは、「党内の分裂を防ぐため」というのが最大の理由でした。
総裁選前倒しを求める声が国会議員と都道府県連の過半数に迫るなか、自ら辞任を選ぶことで混乱の拡大を避けようとした形です。
また選挙での責任を明確にすることで、次の政権への引き継ぎをスムーズに進めたいという思いもあったようです。
7日午後6時から行われた記者会見では、石破茂首相は「国政に停滞をもたらさないことが第一」と述べ、続投への未練がないことを強調しました。
さらに「国民の声に耳を傾け、しかるべきタイミングで身を引くのがリーダーの責任だ」と語り、一定の成果を挙げたうえでの退陣であることを強調しています。
その成果とは物価高対策や日米関税交渉などで結果を残したこと、また野党との協調による予算成立なども含まれていました。
辞任の発表は事実上の「退陣勧告」が成立する前日に行われたことから、石破茂首相としても「追い込まれた」というよりは、「自ら判断した」形にしたかったと見られます。
石破政権の実績と限界
石破政権は短命ではありましたが、いくつかの分野で成果を残しました。
まず、経済政策では物価高騰に対して2万円の給付措置を導入し、特に子育て世帯や住民税非課税世帯に向けた追加支援が評価されました。
また、最低賃金の全国加重平均は過去最大の上昇幅となり、賃上げを重要課題と位置づけた政策が一定の結果を出した形です。
外交面では、トランプ政権との日米関税交渉をまとめ、特に自動車関税の引き下げに道筋をつけた点は大きな功績とされています。
国会運営においても、少数与党という厳しい状況の中、野党と協議を重ねて補正予算案を修正成立させるなど、丁寧な合意形成が目立ちました。
一方で、石破政権が抱えた最大の課題は「選挙に勝てない」という党内の不満です。
2024年の衆院選、2025年の都議選、参院選と連敗を喫し、「勝てるリーダー」としての信頼を失いつつありました。
自民党総裁選の仕組み|簡易型とフルスペックの違い
石破茂首相の辞任により、次のリーダーを決める自民党総裁選が焦点となっています。
この総裁選には2つの方式があり、それぞれ「フルスペック型」と「簡易型」と呼ばれています。
総裁の任期満了時と、急な辞任や死去などのケースで選挙方法が異なり、党内外の注目も集まるポイントです。
通常時の総裁選「フルスペック型」とは?
「フルスペック型」とは、総裁の任期満了に伴って実施される通常の総裁選のことを指します。
この方式では、自民党所属の国会議員票と、全国の党員・党友による「党員票」が合計されて勝者が決まります。
具体的には、国会議員票295票と、全国の党員票295票の合計590票で争われるため、より「国民の声」を反映した選挙方式といえます。
また、選挙期間は12日以上と定められており、候補者たちによる街頭演説や政策討論なども行われるため、国民の関心が高まりやすいです。
この方式が採用される場合、地方の意見が反映されやすく、党内の派閥に属していない候補でも勝機を見いだせるのが特徴です。
たとえば、前回の総裁選(2024年)はこのフルスペック型で行われ、石破茂が地方票を積み重ねて勝利した経緯があります。
ただし、手続きが複雑なため、辞任など緊急事態のときは別の方式がとられることになります。
緊急時に行われる「簡易型」とは?
「簡易型」とは、総裁が任期途中で辞任した場合など、緊急を要する状況で実施される総裁選の形式です。
この方式では、党員投票は行わず、自民党所属の国会議員(295人)と、47都道府県連に3票ずつ配分された「地方票」(計141票)の合計436票で争われます。
つまり、フルスペック型に比べて投票者数が少なく、選挙期間も短縮されるため、スピーディーに次の総裁を選出することが可能です。
この簡易型が採用された代表的な例は、2020年の菅義偉総裁選です。
安倍晋三前首相の突然の辞任を受け、党内の混乱を最小限に抑えるため、短期間で後継者を決める必要があり、簡易型が用いられました。
ただし、党員の意見が反映されにくいため、「民意を無視した密室政治」と批判されることもあります。
そのため、過去には都道府県連が独自に「予備選」を実施して党員の声を集め、地方票の配分に反映させる工夫が取られた例もあります。
今回はどちらになる?選挙方式の行方
今回の自民党総裁選が「フルスペック型」になるのか「簡易型」になるのかは、現在の状況を考えると非常に注目されています。
石破茂首相が任期途中で辞任するという状況であるため、規定上は「簡易型」が適用される可能性が高いです。
実際に2020年の菅義偉総裁選のように、総裁の突然の辞任によって簡易型が採用された前例もあり、今回も同様の判断になると予想されています。
ただし党内では「前回の総裁選では全国の党員投票を含めたのだから、今回も同じく国民の声を反映すべき」との声も根強く存在しています。
また複数の都道府県連が「予備選の実施」を検討しており、地方票を実際の党員の意見で割り振る方式を取る可能性もあります。
選挙方式を決定するのは、党の総裁選挙管理委員会と党執行部ですが、党内の意見の割れや世論の影響も大きく左右しそうですね。
今後の政局はどうなる?解散・総選挙の可能性も
次の総裁が決まったあとは、政権の体制がどう変わるのか、そして衆議院解散や総選挙の可能性があるのかにも注目が集まっています。
今回は任期途中の辞任という異例の展開のため、総裁選後の動きが日本の政治を大きく動かす可能性があります。
新総裁誕生後の内閣総辞職と再組閣シナリオ
新しい総裁が決まると、慣例的に現内閣は総辞職し、国会で首班指名を経て新内閣が発足します。
今回の場合も、石破内閣は総裁選後に総辞職し、新総裁が第103代総理大臣として首相に就任することが見込まれています。
再組閣では、新総裁が人事権をもって閣僚を刷新することが多く、これによって新しい政権の方向性が示されます。
たとえば、保守色を強めたい場合は高市早苗のような人物が重要ポストに就く可能性もあり、改革を前面に出すなら小泉進次郎や若手議員の登用も考えられます。
衆議院解散はあるのか?与野党の戦略を読む
次の総裁が誕生したあと、注目されるのが「衆議院解散はあるのか?」という点です。
結論から言えば、解散の可能性は十分にあります。
なぜなら新総裁が政権基盤を固めるためには「国民からの信任」を得る必要があるからです。
現時点で自民・公明は少数与党であり、与野党のバランスが非常に不安定な中、政権の正統性を確立するには「解散総選挙」が最も直接的な方法です。
次の首相が目指す政策と課題とは?
次の首相が誕生した後、最も注目されるのは「どんな政策を打ち出すのか」という点です。
今の日本が抱える課題は、物価高、少子化、外交安全保障、そして政治不信の解消と多岐にわたります。
新たなリーダーには、これらにスピード感を持って対応することが求められています。
たとえば、高市早苗が総裁に選ばれた場合は、憲法改正や防衛強化といった「保守色の強い政策」が中心になると予想されます。
一方で、小泉進次郎が総裁に就けば、環境政策や子育て支援、デジタル改革など、比較的リベラルで未来志向の政策が前面に出てくる可能性があります。
玉木雄一郎が台頭した場合は、「与野党の協調による実務型改革」という、新たな政権運営スタイルが試されることになりそうです。
まとめ
今回の記事ではこんなことを書きました。以下に要点をまとめます。
- 石破茂首相が2025年9月に辞任を表明し、自民党総裁選が事実上前倒しで実施へ
- 次の総裁候補として、高市早苗・小泉進次郎・玉木雄一郎などが有力視されている
- 自民党総裁選には「フルスペック型」と「簡易型」の2つの方式があり、今回は簡易型の可能性が高い
- 総裁選後は内閣総辞職と再組閣が行われ、新首相のもとで解散・総選挙が実施される可能性もあり
- 新たなリーダーに求められるのは、経済・外交・少子化対策、そして自民党の体質改革
次の日本のリーダーは誰になるのでしょうか。今度こそ国民第一に考えてくれる人が首相になってほしいものです。
最後までご覧いただきありがとうございます。
コメント