秋といえば、美味しい魚が並ぶ季節。サンマやサケ、サバなど、脂がのった旬の魚が食卓に登場する機会が増えてきます。
でもそんな美味しい季節に気をつけたいのが「アニサキスによる食中毒」です。
実はアニサキスによる食中毒は年間で10月が最も多いとされているんです。
その理由はただ魚を食べる機会が増えるから…だけではありません。
この記事では10月にアニサキス食中毒が多発する本当の理由と、どんな魚に注意すべきか、そして自宅でできる簡単な対策までを、わかりやすくまとめています。
ぜひ最後までご覧ください。
なぜ10月に多い?アニサキス多発の2つの理由
秋は「生で食べる魚」が増える季節
10月にアニサキス食中毒が多発する一番の理由は、生で魚を食べる機会が増える季節だからです。
秋はサンマやサケ、カツオなどが旬を迎え、刺身や寿司などの生食メニューが豊富になりますよね。
しかも冷凍技術や物流が進化した今では、水揚げ地から離れた都市部でも「刺身で食べられるサンマ」が手に入りやすくなっています。
その一方で、「新鮮に見えてもアニサキスがいる」ことも。
特に目視で見つけにくい部位に潜んでいるケースも多く、生食文化が普及するにつれて食中毒のリスクも比例して高まっているのが現状です。
気候変動で「S型アニサキス」が拡大中
さらにもう一つの要因として挙げられるのが、S型アニサキスという種類の拡大です。
アニサキスには大きく分けて「P型」と「S型」の2種類があります。
従来日本海にはP型が多く、これは主に魚の内臓に寄生していたため、内臓を除去すればある程度リスクを抑えられていました。
しかし最近海水温の上昇や海流の変化の影響で、S型アニサキスが日本海側にも広がってきているとされています。
S型は魚の「身」にも入り込む性質を持っており、見た目ではわかりにくく、刺身や寿司でそのまま食べてしまうリスクが高くなっています。
福岡ではこの影響を受けて「ゴマサバ(生のサバ料理)」の提供を中止する飲食店も出てきているほどなんです。
海の変化が食卓にまで影響を与えている、そんな時代になってきているんですね。
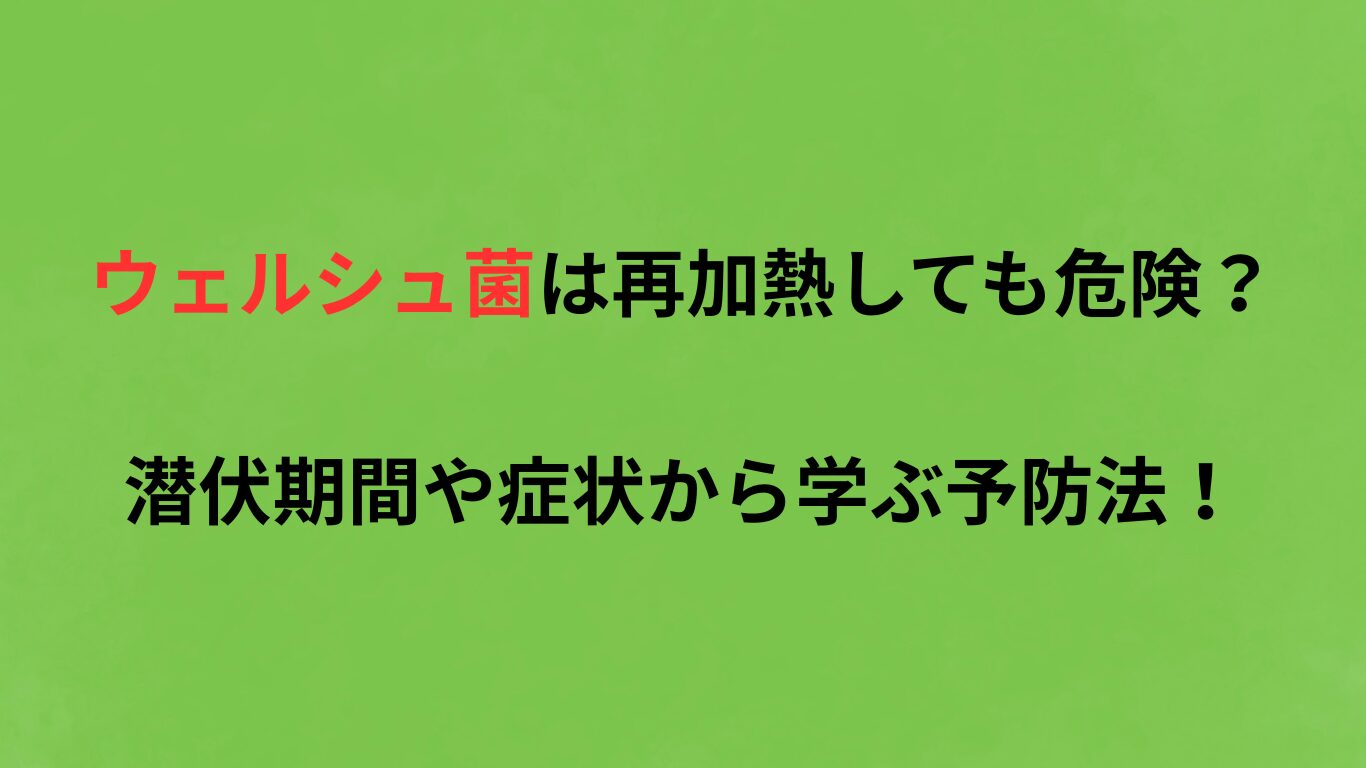
特に注意すべき魚は?危険魚種リスト
アニサキスによる食中毒はどんな魚でも可能性がありますが、特に10月にリスクが高まる魚種があります。
中でも注意したいのは以下の3つ。
- サンマ:秋の味覚の王様。刺身として出されることも増え、寄生の危険性が高い。
- サバ:しめサバに使われるが、酢で締めてもアニサキスは死なない。福岡での食中毒増加の要因にも。
- サケ:生食でも人気だが、輸入品など加熱用のものを誤って食べると危険。
いずれも秋に需要が増える魚ばかり。
美味しくても“調理法”を間違えると、思わぬ健康リスクにつながります。
アニサキス症の症状は「アイスピック級の激痛」
アニサキスに感染すると、胃や腸に虫体が入り込んでしまい、激しい腹痛や嘔吐などの症状が現れます。
その中でも代表的なのが以下の2つです。
- 急性胃アニサキス症:食後数時間以内にみぞおちに激痛が走る。吐き気・嘔吐も併発する。
- 急性腸アニサキス症:食後10時間〜数日後に発症し、下腹部に鋭い痛み。場合によっては入院するケースも。
患者の中には、「胃の中からアイスピックで刺されるような痛みだった」と語る人も。
それほどまでに辛い症状を引き起こすのが、アニサキスなのです。
旬のサンマも要注意!「アイスピックで刺されるような激痛」アニサキス食中毒10月に多発【ひるおび】 #ldnews https://t.co/u3aClpNQXp
— ブライト (@bright_ruruchan) September 26, 2025

アイスピックで刺されるような激痛…想像するのも怖いですね!
実際にあったリアルな体験談
2025年には、テレビ番組『ひるおび』で実際の症例が紹介されました。
40代男性が自宅で食べた「手作りのしめサバ」が原因で食中毒になり、
病院で胃カメラを使ってアニサキスを摘出すると、激痛が嘘のように引いたそうです。
別の50代男性は、出張先でパック寿司を食べた数日後に突然の腹痛。
検査の結果アニサキスが小腸に侵入しており、内視鏡では取り出せず入院することになりました。
どちらも「ありふれた食事」がきっかけだったことが、よりリアルに恐ろしさを伝えてくれます。



パック寿司って案外食べる機会ありますよね…油断も隙もないですね。
自宅でできるアニサキス対策5選
「じゃあ、どうすればいいの?」と思った方のために、自宅でできるアニサキス対策を5つご紹介します。
- 冷凍:マイナス20℃で24時間以上。家庭用冷凍庫では48時間以上が安心。
- 加熱:70℃以上での加熱、または60℃なら1分以上の加熱で死滅。
- 内臓除去:購入後はすぐに内臓を取り除き、鮮度を保つ。
- 目視確認:刺身やサクはよく観察し、白い糸状の虫を見つけたら除去。
- アニサキスライト活用:紫外線でアニサキスが白く浮かび上がるグッズも市販中。
これらを意識するだけでも、アニサキスリスクを大幅に減らすことができます!
アニサキスが寄生している生鮮魚介類を生や、不十分な冷凍・加熱で食べると、食中毒を引き起こします。アニサキスを死滅させるには、冷凍と加熱が最も有効。食品安全委員会はアニサキスのリスクプロファイルを公表しています。食中毒を防ぐために是非ご活用ください。https://t.co/4aamF3Nb7p pic.twitter.com/Q5iTmzxfWe
— 内閣府食品安全委員会事務局_広報 (@FSCJ_PR) August 20, 2025
酢やわさびで死なないって本当?
最後に、多くの人が信じている誤解についてお伝えします。
「酢で締めたから大丈夫」
「わさびをつければ問題ない」
…これ、全部間違いなんです。
アニサキスは酢・醤油・わさびなどの調味料では死にません。
しめサバでも中に潜んでいることはよくあり、実際に発症例も後を絶ちません。
安全に魚を楽しむには、「味付け=安全」ではなく、処理方法と見極め方がカギになるということをぜひ覚えておいてください。
まとめ
今回の記事ではこんなことを書きました!
- アニサキス食中毒は10月に多発する傾向あり
- 原因は「秋の生食文化」と「S型アニサキスの拡大」
- 特に注意が必要な魚はサンマ・サバ・サケ
- 症状はみぞおちや下腹部の激痛、場合によっては入院も
- リアルな体験談からもわかるアニサキスの恐ろしさ
- 対策は冷凍・加熱・目視・内臓除去・専用ライトの活用
- 調味料でアニサキスは死なない!過信はNG!
安心して秋の魚を楽しむためには、ちょっとした知識と予防意識が必要です。
この記事を読んだあなたが、今日から「安全に、美味しく」魚を楽しめますように。
最後までご覧いただきありがとうございます。


コメント