2025年の花火大会で相次ぐ事故、淡路市での爆発…。
原因とされているのは「筒ばね現象」という聞きなれない現象でした。
夏の風物詩である花火大会に、いま何が起きているのでしょうか?
この記事では、
- 淡路市の爆発事故の詳細と当日の様子
- 筒ばね現象の仕組みと防げない理由
- 花火師のリアルな証言と技術継承の課題
- 花火大会の裏にある主催者側の責任
- 観客としてできる安全対策と心構え
について詳しくまとめています。
「まさか」が起きる前に、知っておくべき事実があります。
最後まで読んで、あなた自身と周りの大切な人の安全を守るヒントにしてくださいね。
「筒ばね現象」が原因か 兵庫・淡路市の花火大会で爆発事故https://t.co/yMYgHQgvEc
— MSN Japan (@MSNJapan) August 5, 2025
花火大会の事故が急増!2025年に何が起きたのか?
2025年の夏、全国各地で開催された花火大会で事故が相次ぎ、特に淡路市の爆発事故が大きな注目を集めました。
この章では、実際に何が起きたのかを淡路市の事例を中心に振り返りつつ、観客にも衝撃を与えたその瞬間の様子を紹介します。
淡路市の花火大会で起きた爆発事故の詳細
2025年8月3日、兵庫県淡路市で開催された花火大会で突如として爆発事故が発生しました。
事故が起きたのは打ち上げ開始からわずか10分後。
予定では30分間で5000発を打ち上げる大規模なイベントでしたが、開始直後から異変が起こり、低い位置で花火が爆発するという事態に至りました。
原因とみられているのは、「筒ばね現象」と呼ばれるトラブルです。
これは、花火玉が発射筒から出ないまま筒内で爆発してしまう現象で、今回のように火薬量の不均一さや湿気、設置不良などが重なると起きやすくなります。
打ち上げを担当していた業者も、記者会見でこの現象が原因であったことを認めています。
花火師の安全管理には万全が求められますが、このような現象は経験豊富な職人でも完全に防ぐのが難しいとされています。
幸いにも観客に直接の被害はなかったものの、SNS上では当時の様子が拡散され、「爆発音がすごかった」「現場がパニックになった」といった声が多く見られました。
この事故をきっかけに、花火大会の安全性について改めて見直す動きが広がっています。
被害状況と会場のリアルな様子
爆発事故が起きた瞬間、淡路市の会場では驚きと混乱が広がりました。
観客の多くがスマートフォンで撮影していたため、SNSにはリアルタイムで「燃えてる!」「やばいって!」という声とともに、爆発の様子を収めた映像が次々と投稿されました。
一部の花火は空高く打ち上がらず、地表近くで爆発したため、観客席に近い位置でも強い光と音を感じた人が多く、安全確保に走るスタッフの姿も見られたそうです。
打ち上げ場所のすぐ近くには関係者用の立ち入りエリアがありましたが、そこで花火を操作していたスタッフが避難するような場面も映像に残っています。
このことからも、事故がいかに突然で、予測が難しいものであったかがわかりますね。
幸いにも負傷者は確認されませんでしたが、会場の一部には燃えた痕が残っており、警察や消防による原因調査が急ピッチで進められました。
中止が決定された際のアナウンスでも、観客の安全を最優先にした判断であることが繰り返し説明されていました。
今回の事故は、目立った人的被害こそなかったものの、「夏の風物詩=安全」という認識に揺さぶりをかける出来事となりました。
筒ばね現象の正体と防げない理由とは?
今回の事故の原因とされている「筒ばね現象」は、花火業界でも恐れられている現象のひとつです。
ただし、その仕組みは一般にはあまり知られていません。
ここでは、筒ばね現象がどういうものなのか、そしてなぜ防ぎにくいのかを専門家の視点も交えて詳しく解説していきます。
筒ばね現象とは?専門家が解説するその仕組み
筒ばね現象とは、打ち上げ花火の火薬が正しく爆発せず、花火玉が発射されないまま筒の中で爆発してしまう現象を指します。
本来、花火玉は導火線に点火されると、瞬間的に勢いよく空中へと飛び出し、決められた高さで美しく開花するように設計されています。
しかし、筒ばね現象が起きると、何らかの理由で発射がうまくいかず、花火玉が発射筒に詰まったまま内部で爆発します。
これが爆風や火炎を地上に発生させ、事故やけがにつながる危険性を高めるのです。
火薬量の調整ミス、湿気の影響、筒の設置角度のズレなど、複数の要因が重なって発生するため、1つの対策だけでは完全に防ぎきれないのが実情です。
実際、今回の淡路市の事故でも、花火業者が「火薬の不十分さによる筒ばね現象」と公式に説明しています。
さらに、大玉花火ほど構造が複雑で重量もあるため、この現象が起きやすくなるとも言われています。
専門家の間でも「100%防げるものではない」とされる難しさがあるのです。
花火師の証言「大玉になるほどリスクが高い」
実際に現場で花火を打ち上げている花火師たちは、「筒ばね現象は誰にでも起こりうる」と警鐘を鳴らしています。
関西テレビの取材に応じたベテラン花火師・段克史さんは、「大きな玉になればなるほど筒ばね現象が起きやすくなる」と語りました。
大玉は火薬量が多く、その分、内部圧力も高くなるため、少しの不具合でも暴発につながる可能性が高まるそうです。
また、最近の傾向として「より迫力ある演出」が求められており、10号玉や20号玉といった大玉の打ち上げが増えていることも、リスクの上昇に拍車をかけています。
観客の目を引く演出の裏では、花火師たちが神経をすり減らしながら作業しているという実態があるのですね。
さらに、「花火は自然相手の仕事。湿気や風、気温などで火薬の状態が変わる。どんなに注意しても完璧には防げない」と話す花火師も。
これほどまでに繊細な作業でありながら、見る側の私たちにはその危険性がほとんど伝わっていないのが現実です。

大玉の打ち上げが増えているのも事故が多い原因だったんですね。
技術継承問題と安全管理の現状
今回の事故を通じて、もうひとつ浮き彫りになったのが「技術継承の難しさ」です。
花火は一見華やかですが、その裏には熟練の技術が必要であり、コロナ禍の影響で技術の伝承が途絶えかけている現実があります。
ここでは花火師の世界で今、何が起きているのかを掘り下げていきます。
花火大会の裏側で起きている“技術の空白”
新型コロナウイルスの影響で、ここ数年は全国各地の花火大会が中止されることが続きました。
その結果、多くの花火師たちが仕事から離れざるを得なくなり、現場での実践経験を積む機会が極端に減少しました。
花火というのは、紙の巻き方ひとつ、火薬の配分ひとつで仕上がりや安全性が変わる、とても繊細な伝統技術です。
しかし、数年も実戦から遠ざかれば、技術は衰え、若手への指導機会も激減します。
つまり、コロナ禍は“技術の空白期間”を作ってしまったのです。
また、花火業界そのものが高齢化しており、若手が定着しづらいという構造的な問題もあります。
後継者不足と合わせて、業界全体で技術力の低下が進んでいるという指摘も増えてきました。
花火は機械ではなく「人の手」によってつくられるもの。
そのため、ベテランの勘や経験に頼る部分が大きく、ひとたび経験値が途切れれば、全体の安全性にも大きく影響してしまうのです。
相次ぐ花火大会の事故 原因は「筒ばね」か”紙のちょっとした隙間でも起きる”防ぎきれない暴発 さらに業界が抱える技術継承問題 背景に「コロナによる大会中止」で職人が離職(FNNプライムオンライン)#Yahooニュースhttps://t.co/geH1n73LBv
— F-4N ファントムⅡby高平幸広 (@A6A156699) August 7, 2025
花火師任せにする主催者側のリスクとは?
花火大会と聞くと、花火師がすべてを管理しているイメージがありますが、実はそこに大きな落とし穴があります。
それが「主催者側の安全管理意識の低さ」です。
関西テレビの報道でも指摘されていたように、近年の花火大会では主催者が花火師にすべてを丸投げし、安全対策が形式的になっていたケースも多く見られます。
たとえば、打ち上げ場所や観客席との距離の取り方、火災対策、水上での避難手段など、本来は主催側が入念にチェックすべき項目が、現場に委ねられたままになっていたというのです。
実際、横浜みなとみらいの花火大会では、台船上で火災が発生し制御が効かなくなりました。
このときも、現場スタッフが「海に飛び込んでください」と避難指示を出すような緊急事態になり、事前の避難計画が十分だったのかという疑問が残りました。
また、安全確認に必要な機材や人員が不足していたり、警備体制が不十分だったという報告もあります。
花火師がいかに高い技術を持っていても、主催者がリスク管理に関与しない限り、事故を未然に防ぐのは難しいのです。
今後は「花火を打ち上げるだけ」ではなく、「いかに安全に届けるか」という視点で主催者側も関与を深める必要がありますね。
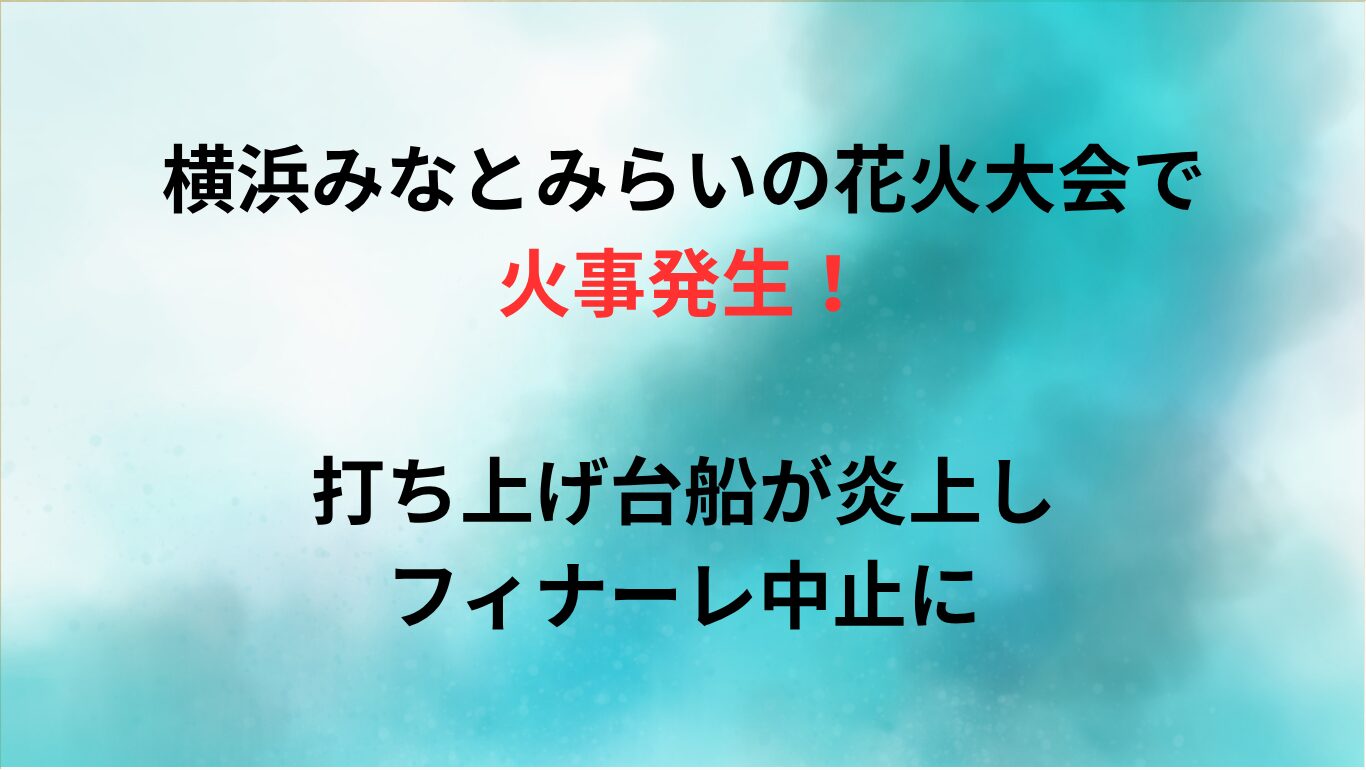
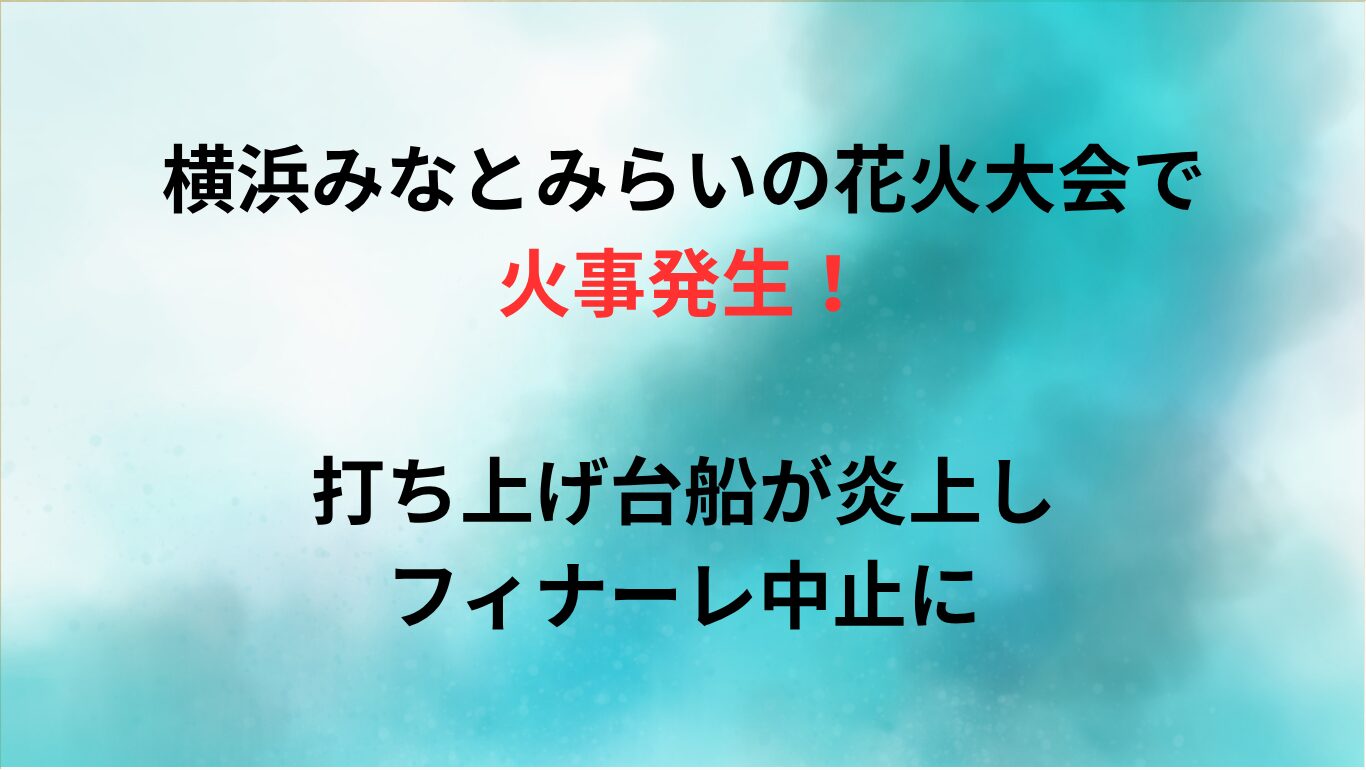
今後の花火大会はどうなる?私たちにできる安全対策
花火大会は夏の風物詩として多くの人が楽しみにしていますが、事故のリスクもゼロではありません。
では、観客である私たちは何ができるのでしょうか?
観客として知っておきたいリスクと対処法
事故を完全に防ぐことが難しい中、観客としても「安全意識」を持つことが求められています。
まず、会場内では必ず案内や注意事項に従いましょう。
特に打ち上げ場所の近くや立ち入り禁止区域に近づかないことは鉄則です。
SNS映えを狙って危険な位置から撮影する行動は、命に関わるリスクを伴います。
また、何か異常を感じた場合はすぐにスタッフに知らせることも大切です。
煙がいつもと違う方向に流れている、音のタイミングがおかしい、火薬の臭いが強いなど、小さな違和感でも事故の前兆かもしれません。
避難経路をあらかじめ確認しておくのも安心材料になります。
家族や友人と一緒に来場している場合は、迷子やパニックにならないよう集合場所を決めておくといいですね。
安全な花火大会を続けていくために必要なこと
花火大会を安全に楽しみ続けるためには、関係者だけでなく、私たち観客を含めた「社会全体の意識」が求められています。
まず、主催者側は花火業者に任せきりにせず、安全マニュアルの見直しや避難訓練の実施など、リスクを前提とした体制づくりが必要です。
警備スタッフの配置や、異常発生時の判断基準を明確にすることも不可欠です。
花火師側も、今後さらに技術を若い世代に伝える取り組みが求められています。
コロナ禍で失われた「現場の経験」を補うには、実践の機会や支援制度が欠かせません。
また、ベテラン職人と若手が一緒に働ける環境づくりも、技術の継承には不可欠です。
観客である私たちも、ただ見るだけでなく「危険と隣り合わせの技術だ」という意識を持って参加することが重要です。
安全が確保されてこそ、花火大会は本当の意味で楽しめるものになりますよね。
今後も美しい夏の風物詩を守り続けるために、私たち一人ひとりが「関わっている」という意識を持つことが、なによりの対策になるのかもしれません。
よくある質問とその答え
Q: 筒ばね現象って素人でも理解できるもの?
A: はい、ざっくり言うと「花火がうまく打ち上がらず、筒の中で爆発する現象」です。
火薬や筒の状態が悪いと起こりやすく、今回の事故もまさにそれでした。
Q: どうして最近、花火大会の事故が増えているの?
A: コロナ禍で大会が中止され、花火師が現場から離れていた期間が長かったことが影響しています。
経験不足や技術の継承不足が事故を招いているケースもあるようです。
Q: 観客としてどんなことに注意すればいい?
A: 立ち入り禁止区域には絶対に近づかず、案内に従って行動することが基本です。
異常を感じたらすぐにその場から離れるなど、自衛意識を持つことが大切です。
Q: 今後、花火大会って中止が増えそう?
A: 安全面への不安から、規模縮小や中止の判断がされるケースも増える可能性があります。
そのため、運営体制や技術継承への支援が社会的にも求められています。
Q: 筒ばね現象は完全に防げないの?
A: 専門家も「完全には防げない」と話しています。
複数の要因が重なることで発生するため、万全を期してもゼロにはできないのが実情です。
まとめ
今回の記事ではこんなことを書きました。以下に要点をまとめます。
- 2025年、淡路市などで花火大会中に爆発事故が発生
- 原因とされる「筒ばね現象」は、花火玉が筒の中で爆発してしまう危険な現象
- 筒ばね現象は火薬量や設置の微妙なズレで誰にでも起こりうる
- 花火師の証言では、大玉になるほど発生リスクが高まるとのこと
- コロナ禍の影響で技術継承が進まず、事故防止が難しくなっている
- 主催者の安全管理任せが事故につながる可能性も
- 観客自身ができる安全対策も多数存在する
花火大会は一見すると楽しいイベントですが、裏側には高度な技術と緻密な安全管理が欠かせません。
事故を減らしていくには、業界全体の意識改革とともに、私たち観客側の理解と協力も必要不可欠です。
最後までご覧いただきありがとうございます。




コメント