小泉進次郎氏陣営の投稿依頼問題とは?
2025年の自民党総裁選を舞台に、ネット上を騒がせた「やらせコメント問題」。
小泉進次郎農水相の陣営が、配信動画に対して称賛コメントを依頼していたことが明るみに出ました。
"小泉進次郎氏陣営の投稿依頼問題、選挙プランナー事務所が謝罪「例文案を作成したのは当社従業員」" https://t.co/mLEOYpuPUs
— 猫野クロちゃん (@nekonosan1) October 14, 2025
選挙違反はトップの責任だろ。
問題が発覚した経緯と騒動のきっかけ
この問題が最初に報じられたのは「週刊文春」によるスクープでした。
内容は、小泉進次郎氏の陣営が総裁選の際、配信動画「ニコニコ生放送」上に、彼を称賛するコメントを支援者らに依頼していたというものでした。
その依頼文には、具体的なコメント例文まで添えられており、視聴者の自発的な意見ではなく、あらかじめ用意された“好意的な投稿”が行われていたことが明らかになりました。
このような“やらせ投稿”は、世論操作とも受け取られかねず、報道直後から大きな波紋を呼びました。
コメント例文の内容とSNSでの投稿実態
実際に使用されたコメント例文の中には、「小泉さんしかいない!」「あの石破さんを説得したのスゴい」「総裁まちがいなし!」など、明らかに支持を煽る内容が含まれていました。
全部で24パターンの例文が用意されていたとされ、その一部には他候補者を貶めると受け取られかねない表現もあったのです。
特に注目を集めたのが、「ビジネスエセ保守に負けるな」といった文言。
これは高市早苗氏を意識したのではないかという憶測を呼び、さらなる議論を呼ぶことに。
このような“操作された称賛”が、SNSという拡散力のあるメディアで行われたことが、問題の根深さを物語っています。
問題の詳細が明らかになる中、関係者からの謝罪や説明が相次ぎました。
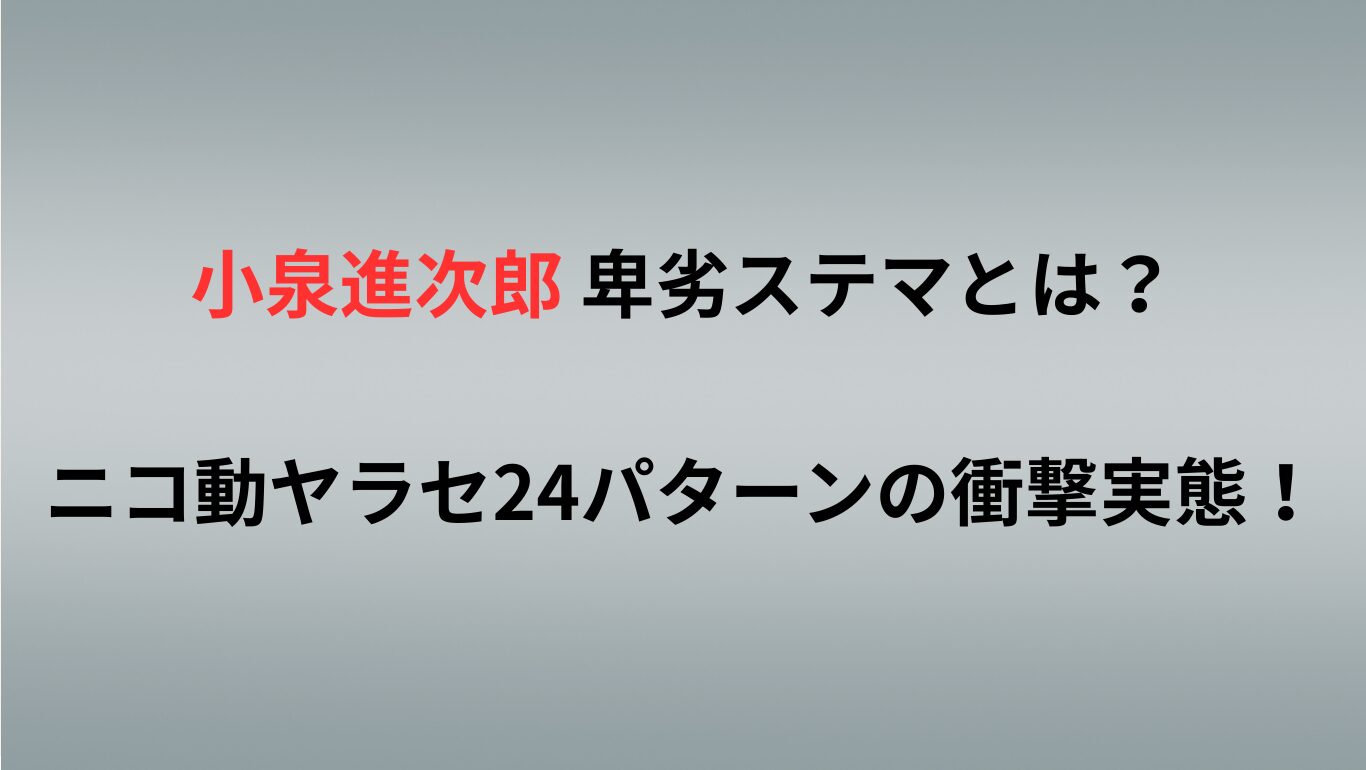
選挙プランナー事務所が謝罪した理由とは?
問題の発端となった「やらせコメント」の例文を作成していたのは、選挙プランナー・松田馨氏が代表を務めるコンサル会社「ダイアログ」でした。
小泉進次郎氏陣営の投稿依頼問題、選挙プランナー事務所が謝罪「例文案を作成したのは当社従業員」 : 読売新聞https://t.co/3NSavAAzrq
— すててお (@93kabuo) October 14, 2025
松田馨氏とダイアログ社の対応内容
2025年10月14日、ダイアログ社は公式サイト上に松田馨氏の名前で謝罪声明を掲載しました。
その中で、「例文案を作成したのは、当社の従業員である」と明確に認めた上で、「一部に行き過ぎた表現が含まれていたことは事実」として謝罪。
また、「他の候補を貶める意図はなかったとはいえ、そう受け取られかねない内容だった」とも述べ、責任を全面的に受け止める姿勢を示しました。
加えて、記事によって関係者の名誉が損なわれているとし、訂正や名誉回復も求めました。
責任を取る形で、ダイアログ社は複数の再発防止策を発表しています。
再発防止策として打ち出された具体的な対策
同社が打ち出した主な再発防止策は以下の4つです。
- 社内ガイドラインの策定
- チェック体制の強化(複数人による確認)
- 社員研修の実施
- 経営責任の明確化と役員報酬の減額
牧島かれん氏の関与は?報道と現実のギャップ
一部報道では、「牧島かれん氏がコメント例文を作成し、投稿を主導した」とされていましたが、実際にはその表現が大きく誤解を生んでいたようです。
誰が作成しようが小泉陣営の広報は牧島かれん。その親分は小泉進次郎。ステマ戦略の責任は免れない。
— 鰻犬7号 (@unagi_inu_No_7) October 14, 2025
ー
小泉進次郎氏陣営の投稿依頼問題、選挙プランナー事務所が謝罪「例文案を作成したのは当社従業員」(読売新聞オンライン) https://t.co/f6wk1cdLet
広報班長としての立場と辞任の理由
牧島かれん元デジタル相は、小泉陣営の総務・広報班長を務めていました。
問題の発覚後、自身の関与について問われる中で、「例文作成には関わっていない」と主張。
しかし、「確認が不十分だった」として、騒動の責任を取り辞任しました。
さらに、騒動の影響で脅迫メールなども届いていたと報じられており、事態の深刻さが伺えます。
報道の表現が事実と異なるとされたポイント
ダイアログ社の声明では、「牧島氏がコメント例文を作成し、投稿を主導したかのような表現は事実と異なる」と明言されています。
つまり、牧島氏の事務所が例文を送付したのは事実でも、それは社内の作成物であり、彼女本人が主導したわけではないという立場です。
報道による名誉毀損に対し、強い抗議の意志もにじませた声明文となっていました。
今回の件は、報道と事実のギャップがどれだけ人を傷つけるかを改めて浮き彫りにしています。
今回の件から見えるSNSと政治の危うい関係
この問題は単なる“投稿依頼”にとどまらず、SNSを活用した選挙戦術そのものに警鐘を鳴らす事例となりました。
ネット選挙におけるステマ問題とは?
SNS上での選挙活動は、情報の伝達速度と拡散力が大きな武器になります。
しかし、称賛コメントを“依頼”し、“例文付き”で投稿させる行為は、いわば政治版の「ステルスマーケティング」。
それが有権者を意図的に誘導し、判断を歪める可能性があるからこそ、社会全体で透明性が求められているのです。
今後のSNS運用で求められる倫理と対策
これからの時代、SNS運用には以下のような倫理とルールが必要とされます。
- 投稿依頼の可視化(誰が依頼したか)
- コメント内容の自主性尊重
- 事前の監修・社内審査体制
- 誰もがアクセスできるガイドラインの整備
特に若年層の政治参加が進む中で、こうしたリテラシー教育も同時に必要になってくるでしょう。
まとめ
今回の記事ではこんなことを書きました。以下に要点をまとめます。
- 小泉進次郎氏陣営が称賛コメントを依頼していたことが発覚
- ダイアログ社の従業員が例文を作成していたことを認め謝罪
- 松田馨氏は「責任はすべて自分にある」として再発防止策を公表
- 牧島かれん氏は投稿を主導しておらず、確認不足を認め辞任
- SNSと選挙活動の関係に新たな課題が浮かび上がった
選挙がより公正で透明なものになるために、私たち有権者の目も重要です。
選挙プランナーのせいにしようとしているように見えますが、結局一番の責任は小泉進次郎氏にあるのでは?
最後までご覧いただきありがとうございます。
コメント