小泉進次郎氏“称賛コメント依頼”問題とは?報道とSNSの反応を整理
2025年の自民党総裁選のさなか、小泉進次郎農林水産相の陣営が、ニコニコ動画での“称賛コメント”を依頼していたと週刊文春が報道。
事実をおおむね認めた発言も飛び出す中、SNSでは「ステマ」「やらせ」といった批判が広がっています。
称賛コメント依頼の発端は週刊文春の報道
週刊文春の報道によると、小泉進次郎氏の支援者である牧島かれん議員の事務所が、関係者に対して小泉氏を好意的に評価するコメントを投稿するよう要請。
メールには「総裁まちがいなし」「ビジネスエセ保守に負けるな」といった例文が添付されていたとされます。
この内容が発覚し、ネット上では一気に炎上。
批判の声が広がる中で、メディアもこの件を大きく報じることとなりました。
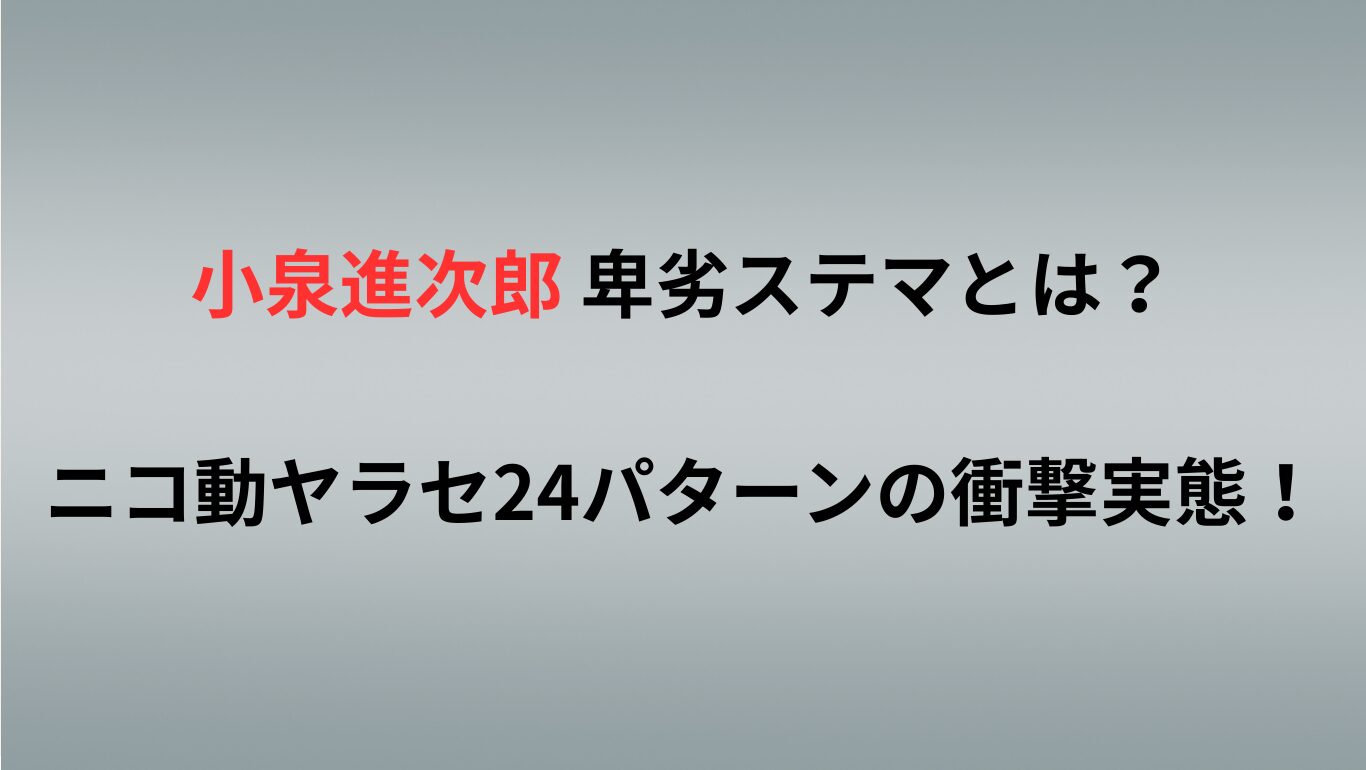
陣営幹部が事実を認め、小泉氏も会見
報道を受け、小泉氏陣営の小林史明衆院議員が25日夜、「事実関係をおおむね認める」とメディアに説明。
翌日、小泉氏本人も記者会見にて、「支援する議員の事務所が独自の判断で送った」と釈明しました。
さらに、「一部に行き過ぎた表現があった」「再発防止を徹底する」とコメント。
ただし、SNS上での発信にはこの件への言及がなかったため、「説明責任を果たしていない」との批判は収まりませんでした。
小泉進次郎
— あーぁ (@sxzBST) September 26, 2025
「私自身も知らなかったこととはいえ総裁選に関わる事でもありますので申し訳なく思います。再発防止を徹底して引き続き緊張感を持って総裁選に臨みたいと思います」
総理大臣になる人が知らなかった、これから気を付けるで済むと思ってるの?
出馬辞退して下さい pic.twitter.com/olH0CPH47E
SNSの反応と“信頼失墜”の現実
「説明がないのはおかしい」ネットで怒りの声が噴出
小泉氏のSNS投稿にはこの問題への直接的な説明がなく、ユーザーからの不信感は一層高まりました。
SNSでは次のような反応が目立ちました。
- 「説明なしで動画投稿?信頼できない」
- 「ステマや自演は問題だと思わないのか」
- 「総裁選、辞退すべき」
このような声が溢れる中で、政治家としての誠実さに疑問を抱く人も増えている印象です。
総裁選、逃げる気マンマンなのかな? https://t.co/td8ed9HveV
— ラビリンス (@glmGfuf0xy2jotw) September 26, 2025
他陣営や党幹部も静かに反応
他の総裁選候補者の陣営も、一定の距離を取りつつも反応を示しました。
- 高市早苗氏の陣営は、「選挙管理委員会に委ねる」と冷静な姿勢
- 小林鷹之氏の陣営は、「特にコメントしない」とノーコメントを貫く
また、自民党総裁選の選挙管理委員長である逢沢一郎氏も、「陣営間の感情的対立をあおらないように」とコメントしています。
党内では加藤勝信財務相(小泉氏の選対本部長)が「重く受け止めている」と発言し、再発防止の必要性を強調しました。
これは、当然ながら牧島かれん個人の問題ではない。小泉選対の組織ぐるみの悪質さを示している。
— 北村晴男 (@kitamuraharuo) September 26, 2025
これを大問題と考えない自民党国会議員は、自由民主党を名乗る資格無し。 https://t.co/0P3RWr7koS
称賛コメント依頼は違法なのか?
法律上は「グレーゾーン」の可能性
公職選挙法において、SNSを活用した選挙活動は合法とされています。
ただし「報酬を伴う投稿依頼」や「他候補への誹謗中傷」は違法とされる可能性があります。
今回のケースでは報酬のやりとりは明らかになっておらず、法律違反とは断定できないグレーな領域に位置しています。
一方で、「違法でなければいいのか?」という視点も多く、ネット上では法律の問題以上に倫理観の欠如が問われています。
誠実さと透明性が政治家の評価を左右する
SNSは、政治家が有権者と直接つながる貴重な手段です。
しかしその一方で、不自然な「演出」や「操作」が透けて見えると、一気に信頼を損なうリスクも高くなります。
今回の称賛コメント依頼問題は、まさにSNS時代の政治家のリスクマネジメントを象徴する事例です。
本当に支持を得たいのであれば、裏での依頼ではなく、正面からの言葉と行動で信頼を築くべきなのかもしれません。
政治とSNSに求められる“新しい倫理観”
ネット戦略か情報操作か、その線引きとは?
政治家のSNS活用は今後も広がっていくことが予想されます。
ですが、どこまでが“戦略”で、どこからが“情報操作”なのか、その線引きがますます求められる時代になっています。
今回の件はその境界線の曖昧さを浮き彫りにした形です。
今こそ問われる「信頼を得る言葉と姿勢」
小泉氏の陣営が今回のような対応を取ったことで、支持層からも「残念だ」という声が出ています。
誤解を恐れず、誠実に、透明に。
そのような言葉と姿勢こそが、今後の政治家にとっての“最強の武器”になるのかもしれません。
小泉進次郎氏もこんな姑息な手を使わなくても国民から支持され、信頼されるような政治家になってほしいものですが……難しそうですね。
最後までご覧いただきありがとうございます。
コメント