2025年秋、米の価格が再び上昇しはじめています。
スーパーでは5kg4000円を超える商品も並び、家計を直撃しているこの状況…。
「なんでこんなに高いの?」
「いつまで続くの?」
「節約ってどうすればいいの?」
そんな疑問や不安を感じている方に向けて、この記事では以下のポイントを詳しく解説していきます👇
- なぜ米価格が再び上昇しているのか?
- 2025年秋に日本の食卓に迫る“3つの危機”とは?
- 政府や農家の対応策と、新品種の可能性
- 今からできる!消費者目線の節約術と賢い買い方
ぜひ最後までご覧ください。
米価格 再上昇でどうなる日本の食卓?
再び上昇を始めた米価格に、多くの家庭が不安を感じています。スーパーでは5キロ4000円を超える価格帯の商品も登場し、食卓への影響が現れ始めています。
参考になります。
— ヒロ (@taaffeite_) September 8, 2025
9/5 日経にこういう記事出てました。米は構造的な農業の高齢化で供給量増やせないとかあるかもですね。
コメ価格、秋以降に再上昇か 見通し指数過去最大の上げ幅:日本経済新聞https://t.co/DYzf6ig1Cv
スーパーの米が高すぎる!5kg4000円時代に突入した理由
米価格が上がっている最大の理由は、新米の価格が軒並み高騰しているからです。
その背景には、猛暑と渇水による不作があります。この夏は各地で記録的な暑さとなり、イネの生育に悪影響を与えました。
特に神奈川県平塚市などでは、実入りが悪く品質の低下も報告されています。農家の間では「粒が小さい」「白く濁る」「もみが空」という声が多く、不作の影響が色濃く出ています。
加えて、農協(JA)が農家に前払いする「概算金」が過去最高水準に引き上げられたことで、新米の仕入れ価格自体が上昇。その結果、スーパーでの販売価格も引っ張られるようにして上がっています。
たとえば2025年8月末のデータでは、スーパーでのコメの平均価格は5kgあたり3891円。中でも銘柄米は4272円という高価格帯となっており、日々の買い物にもじわじわと影響が出てきています。
今後も価格が下がる見通しはなく、「高いけど買うしかない」という状態が続きそうです。
案の定、小泉推しの動きが出始めてますが米騒動で成果だしたと言われてるが備蓄米放出しただけ。
— りょう (@astiflat) September 7, 2025
そして、備蓄米は余ってるし結局米の価格は再上昇で変わらないまま。
農家からも批判出てるし、過去実績は謎のポエムとレジ袋やマクドナルドのプラストロー廃止だぞ。
ポンコツ据えたら日本終わるって https://t.co/KK1qrYhez4
JAの概算金が爆上がり?卸業者との集荷競争が激化
米価格の高騰には、JA(農協)と卸業者の間で繰り広げられている「集荷競争」も大きく関係しています。
JAは農家から米を買い取る際に、実際の販売価格が確定する前に「概算金」という形で前払いをします。今年はその概算金が全国的に引き上げられていて、過去最高レベルにまで達している地域もあるんです。
この背景には、JA以外の業者が農家から米を直接買い取ろうとする動きの活発化があります。JAとしては農家を囲い込むためにも、より高い金額で仮払いをする必要があり、結果的に市場価格が吊り上がるという構図が生まれてしまっています。
さらに、猛暑による収穫量減や品質低下の懸念が広がっている今、「良質な新米を少しでも多く確保したい」という思惑から、各業者の動きがより加速しています。
JAの高い概算金に引っ張られる形で、他の卸業者も価格を上げざるを得ず、それがそのまま消費者の購入価格にも反映されているのが現状です。
つまり、米の値上がりは単なる気候だけの問題ではなく、市場の競争構造が複雑に絡み合っているのです。
結局、米の価格が下がらないのか。
— しょーけんTV (@shoken_FP) September 6, 2025
コメ価格、秋以降に再上昇か:日本経済新聞 https://t.co/lq4z7BxrXY
家計の悲鳴と主婦のリアルな声を拾ってみた
米の値上がりによって、日常の食費を見直さざるを得ない家庭が増えています。
「毎日食べるものだからこそ、ちょっとの値上がりでも家計に響く」
そんな声が主婦層を中心にSNSでも多く見られます。5kgで4000円近い価格になると、1日2合使う家庭では1か月で1袋消費するため、月に約4000円がコメ代だけにかかる計算になります。
また、「安い米を探して3軒のスーパーをはしごしている」「ブレンド米を買うようになった」というような行動変化も目立ちます。これまでブランド米にこだわっていた人たちも、「少しでも安いほうを」とシフトしつつあるのが現状です。
一方で、「食費を削りすぎると栄養バランスが心配」という声もあり、ただ節約するだけでは済まされないジレンマも浮かび上がっています。
こうした“日常の工夫”や“節約ストレス”が重なることで、物価高はただの数字の問題ではなく、生活の質に直結する深刻な問題として広がっています。

以前は近所のドラッグストアで5㎏最安値で1,300円だったのが一気に4,000円まで値上げはかなりキツイです。今年日本産のお米を海外にかなりバラまいていたのが本当理解不能でした。しかも売られていた価格も日本より安いみたいです(海外在住日本人談)どうしてそんなことを政府はしたのでしょうか。
2025年秋に押し寄せる3つの危機!
物価高が続く中、米価格の再上昇はただの一現象ではありません。その背後には、日本の食と経済に深く関わる「3つの危機」がじわじわと迫ってきています。
危機①:新米価格の高騰が止まらない理由とは?
新米の価格が高止まりしているのは、単なる一時的な問題ではありません。
大きな要因のひとつが、生産コストの増加です。肥料や資材の価格が年々上昇しており、農家の経営を圧迫しています。そこに加えてJAによる概算金の引き上げが起こり、全体の流通価格が一気に跳ね上がる形となりました。
また政府による備蓄米の放出は一時的な価格安定に効果を見せましたが、新米の流通が始まると同時に価格は再上昇。「買い控え」どころか、「早めに買わなきゃ値上がりするかも」という心理も働き、需要が加速するという皮肉な状況にもなっています。
さらに注目すべきは、「集荷価格の過熱競争」です。JAと卸業者がより高い価格で新米を買い取ろうとする動きが加速し、それが価格高騰に拍車をかけています。
今のところ価格が落ち着く兆しは見えておらず、「今年の新米は高いのが当たり前」という前提で動いている市場関係者がほとんどです。
コメ価格は5キロ5000円超で推移。
— 翔ちゃん (@sho_nishikawa_) September 1, 2025
備蓄米放出で一時下がったが、供給不足と流通・精米・物流の制約、概算金上昇で再上昇。
消費者はふるさと納税で早め確保。
政府は備蓄米販売延長や概算金改正で対応も、生産者減少や気候変動、人手不足で短期の価格低下は難しい。https://t.co/Y1Sa0wyARq
危機②:猛暑と渇水がイネに与えるダメージ
2025年の夏は記録的な猛暑と渇水に見舞われ、イネの生育に深刻な影響が出ました。
たとえば神奈川県平塚市では「実が入らない」「稲穂が白濁する」といった症状が相次いで報告されました。イネの成長に必要な水が不足したことに加え、田んぼの水温が40度に達する日もあり、冷却が間に合わなかったことが原因です。
また実際に農家からは「10%以上の減収になりそう」「品質が落ちてしまい売値も下がるかも」という不安の声が多数寄せられています。
品種によっては、暑さに弱いものもあり、収穫量・品質ともに安定しない年になっているのが現状です。
このような気候によるダメージは、全国各地で見られており、「収穫できる米そのものが少ない」という、いわば“供給不足”の状態を生んでいます。
供給が少なくなれば、当然価格は上昇します。つまり気象による生産トラブルも米価格再上昇の一因となっているのです。
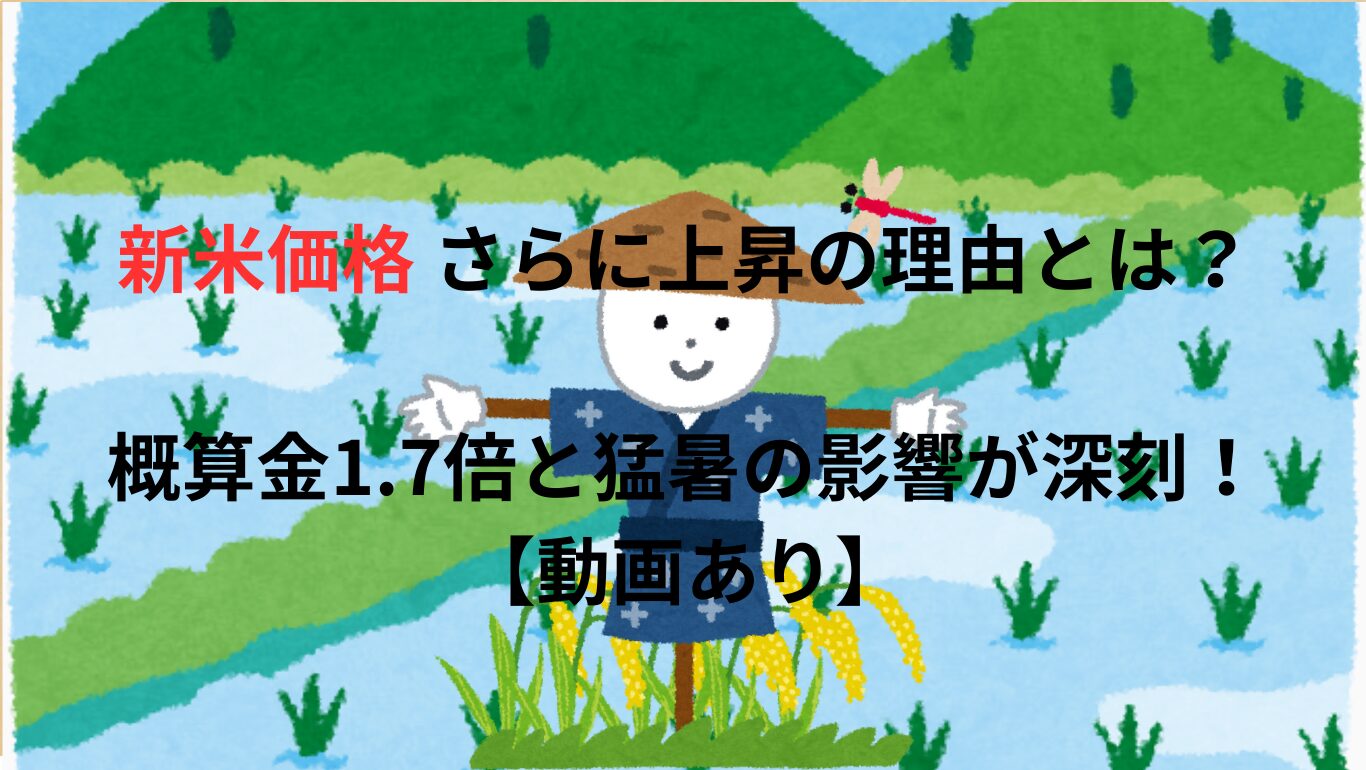
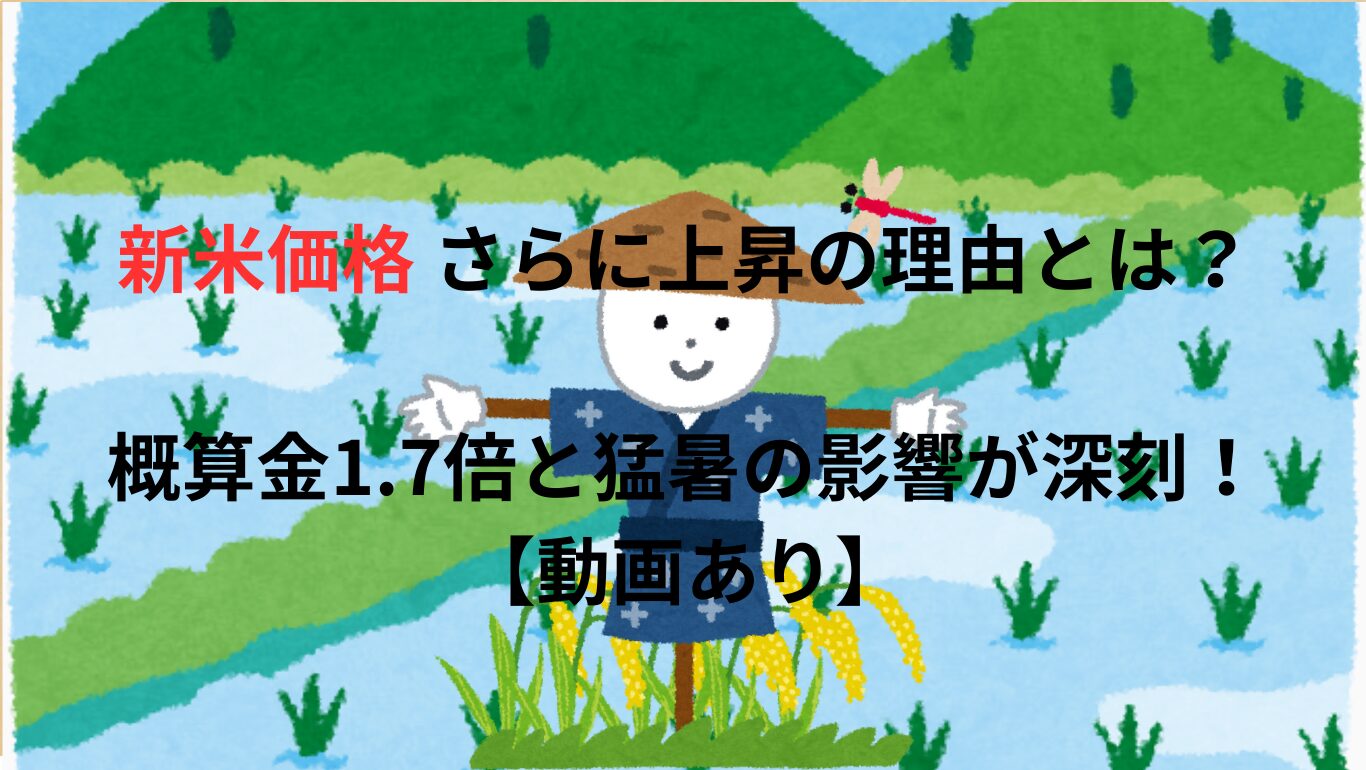
危機③:トランプ関税と円安がダブルで直撃中
米価格の再上昇には、実は“海外”の影響も無視できません。特にトランプ元大統領の再登場による関税政策と、円安の進行がダブルで直撃しているんです。
2025年夏、日本とアメリカの間で関税交渉が行われ、自動車関税の引き下げには成功したものの、その代償として巨額の対米投資が発表されました。この結果、国内の経済負担が増し、円安がさらに加速。
輸入資材の価格も上昇し、米作りに使う肥料や燃料のコストが上がってしまいました。
そして今円安によって外国産のコメや代替食材の輸入コストも高騰。輸入に頼れない状況の中で、「国内米に集中せざるを得ない」という構造が、さらに価格を押し上げています。
さらに懸念されるのが、トランプ政権の再交渉リスクです。
専門家からは「この合意はまだ決着していない」との声もあり、今後また関税率が上がれば、米価だけでなく幅広い物価全体に影響が及ぶ恐れもあるとされています。
政府・農家・消費者のリアルな対応策とは?
米価格の高騰という状況の中で、政府も農家も、そして私たち消費者も、なんとか現状を乗り切ろうとしています。
農水省の緊急対応策と備蓄米の行方
政府はコメ価格の急騰に対応するため、さまざまな緊急策を打ち出しています。
まず注目されたのが、政府備蓄米の放出です。
これにより一時的に市場の供給量が増え、価格上昇を抑える効果がありました。
しかし、新米が市場に出回ると同時に価格は再上昇しており、抜本的な解決には至っていないのが現状です。
また、政府はコメの「増産支援」方針を打ち出し、いわゆる減反政策を見直す動きに出ています。これまで“作らないようにする”ことで価格を安定させてきた政策が、逆に“作らせる”方向に転換してきたのです。
農林水産省は新年度の予算案で、多収品種の開発費に8億円、種子生産の体制強化に19億円を盛り込み、品種開発と増産を本格的に後押ししています。
ただしこれらの効果が現れるには時間がかかるため、当面は備蓄米と消費者行動のバランスがカギになりそうです。
注目の新品種「えみほころ」「そらきらり」の可能性
猛暑や渇水による品質低下への対策として、いま注目されているのが“暑さに強いコメの新品種”です。その中でも特に話題なのが、「えみほころ」と「そらきらり」という2つの多収品種です。
「えみほころ」は、猛暑の町として知られる埼玉県熊谷市で生まれた新品種。水温40度にも達する過酷な環境下でも安定して育つことから、「暑さに最強」とも言われています。粘りと甘みのバランスも良く、“笑みがほころぶ味わい”というネーミングも印象的です。
一方の「そらきらり」は北海道で開発された業務用向け品種で、同じ面積で約2割多く収穫できるのが特徴。管理も簡単で、苗の量も少なくて済むため、生産コストを抑えることができ、農家からの支持も高まっています。
これらの新品種は、すでに各地で試験的な栽培が始まっており、来年以降は本格的な作付けが進む見込みです。
暑さや気候変動に強く、収量も多いこれらの新品種が普及すれば、将来的には米価格の安定にも大きく貢献するかもしれません。
業務用米の「もえみのり」なら、田植えすら不要な多収穫品種だったりする。最近あまり見かけなくなったが。
— 復旧テスト中 (@toshio16369) November 3, 2024
えみほころ・そらきらり…お米の新ブランドすくすく 勝負のカギは味じゃない – 日本経済新聞 https://t.co/3KZiZ0N57j
消費者が今できる5つの節約術と買い方のコツ
米価格の高騰は避けられない状況ですが、だからこそ「今できる工夫」で乗り切ることが大切です。
消費者目線でできる節約術と賢い買い方のコツを5つご紹介します。
1. ブレンド米や業務用米を活用する
銘柄米にこだわらず、ブレンド米や業務用米を選ぶことで価格をかなり抑えることができます。
味も意外と良く、炊き方を工夫すれば違和感なく食べられます。
2. 大容量パックを家族や近所とシェアする
10kgや20kgの大容量パックは割安ですが、保存が難点。
家族や友人とシェアして購入すれば、コスパも良くなります。
3. ふるさと納税を活用する
コメはふるさと納税の定番返礼品。
自己負担2000円で大量の米を手に入れられるので、実質かなりお得です。
4. スーパーの値引き時間帯を狙う
夕方以降のタイムセールで、米が値引きされていることも。
いつ、どこで安くなるかをチェックしておくのがコツです。
5. 無洗米で水道代と手間を節約
無洗米は少し割高に感じますが、手間や水の使用量を考えるとトータルでは節約になることもあります。
「高いから我慢」ではなく、「工夫して乗り切る」ことで、米のある生活を維持できるかもしれません。



先日初めてブレンド米を購入したのですが、割れ米はあるわパサパサしてるわ…悲しかったです。でも仕方ないですね。
まとめ
今回の記事ではこんなことを書きました。以下に要点をまとめます。
- 米価格が再び上昇し、5kgあたり4000円を超える事例も発生
- 高騰の原因は猛暑や渇水による不作、JAの概算金引き上げなど
- 米価上昇がもたらす3つの危機は「新米高」「気候変動」「関税と円安」
- 政府は備蓄米の放出や増産支援、新品種の開発を進行中
- 暑さに強く多収な品種「えみほころ」「そらきらり」に注目が集まる
- 消費者はブレンド米の活用、ふるさと納税、大容量の共同購入などで対策を
今後、米の価格がどう推移していくのかは誰にも予測できません。
だからこそ、正しい情報をキャッチしつつ、できる工夫を積み重ねていくことが大切ですね。
最後までご覧いただきありがとうございます。





コメント