2025年の新米価格が今年はさらに上昇すると話題になっています。
農家に支払われる「概算金」が前年比1.7倍以上になり、加えて猛暑や水不足など天候の影響も重なって、5kgあたり4000円を超える価格帯が当たり前になってしまうようです。
「これじゃあ買えない」「でも農家も大事」と、複雑な思いを抱える消費者の声が続出しています。
この記事では…
- 新米価格が上昇している背景とは?
- 農家と消費者、それぞれの立場から見る影響
- スーパーや通販での価格動向はどうなっている?
- 少しでもお得に買うにはいつ・どこで買えばいい?
- 備蓄米やブレンド米など代替の選択肢は?
…などをわかりやすく解説しています!
ぜひ最後までご覧くださいね。
新米 価格 さらに上昇の理由とは?
今年の新米価格がじわじわと上昇している理由には、いくつかの重要な要素が絡んでいます。
中でも「JAによる概算金の大幅な引き上げ」と「天候による不安定な供給」が大きく影響しています。
JAの概算金が過去最高レベルに引き上げ
新米価格が上昇している最大の要因は、JA(農協)が提示する「概算金」の異例の高さです。
概算金とは農協がコメ農家からコメを集める際に、前払いで支払う仮の金額のことです。
今年は北海道で70%以上新潟では35%もの上昇幅となり、「ゆめぴりか」が3万円、「ななつぼし」が2万9000円という、前年と比べて1.7倍以上の金額が提示されています。
これは昨年JAが十分な量のコメを集められなかった反省から、農家に対して早期確保のために高額を提示している背景があります。
結果として、この概算金の高騰がそのまま店頭価格に反映される見通しとなっているんですね。
農家が歓迎する背景とは?
JAによる概算金の引き上げは農家にとっては明るいニュースとなっています。
その理由は「生産コストの上昇」に対してようやく収入面での補填が見込めるからです。
実際に旭川市の農家・川添宏明さんは、「機械の購入もあり、これまで利益が減る一方だったが、今年は余裕をもって次に進める」と前向きな声を寄せています。
ここ数年、農業を取り巻く環境は厳しく、肥料・燃料・資材の高騰により利益が圧迫されていました。
そんな中での概算金アップは「農業継続のモチベーション」や「次世代への投資」につながる可能性もあるんです。
とはいえこれはあくまで“生産者側”の視点。
この価格上昇が消費者の財布にどう影響するのかも重要な論点です。
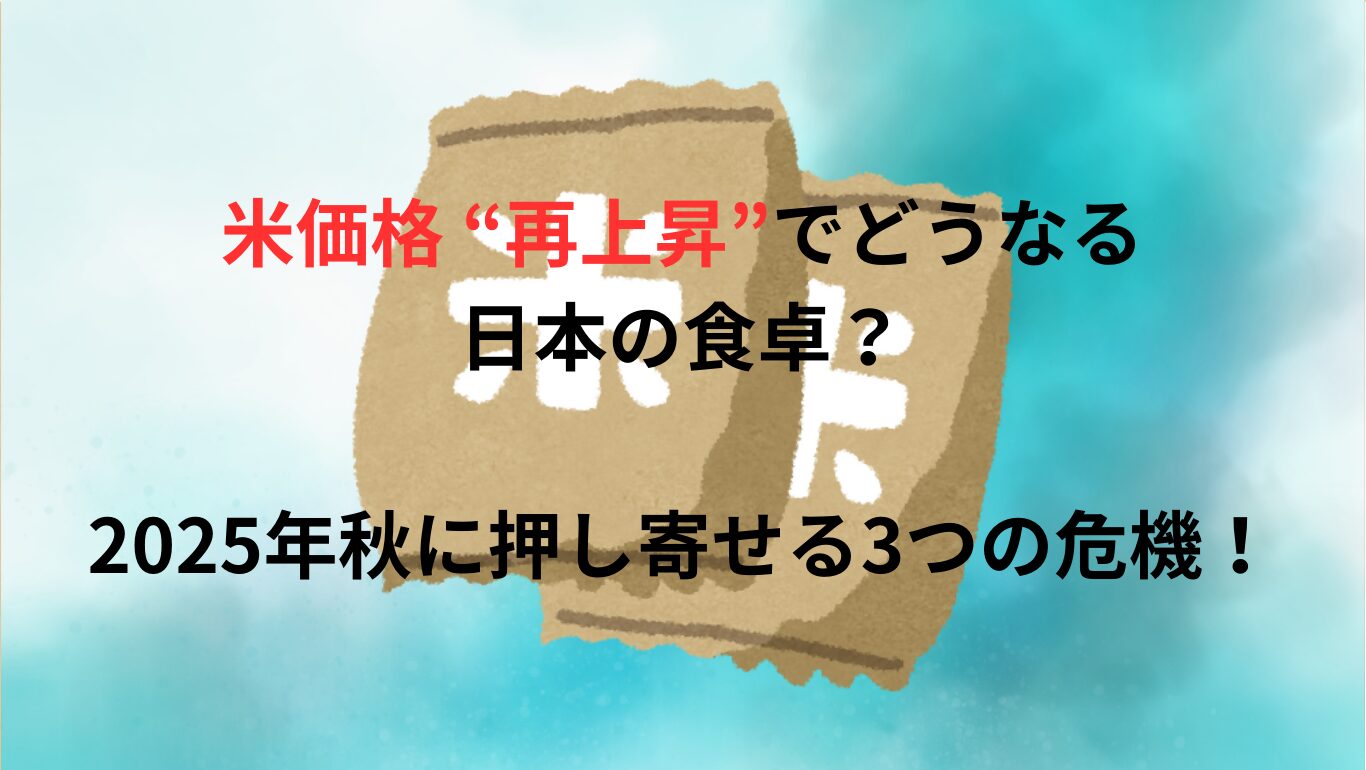
概算金と店頭価格の関係性は?
「概算金が上がったら、店頭の米も確実に高くなるの?」と気になる方も多いですよね。
実はそう単純でもないんです。
たしかに概算金の上昇は農協が農家から米を仕入れる価格が上がるということなので、基本的には店頭価格にも影響します。
でも今年の状況をよく見ると、もう少し複雑なんです。
たとえば、酪農学園大学の相原教授は「概算金は上がっても、追加金を含めた前年と比べて最終的な農家収入は大きく変わらない」と指摘しています。
つまり、概算金が高く見えても、消費者側の負担は“爆上がり”するわけではないという見方もあるんですね。
実際、全国のスーパーでの価格は2025年3月~5月は4000円台まで上昇しましたが、その後備蓄米が流通し始めた6月以降は3000円台後半に落ち着いています。(※地域差があります)
とはいえ今年の天候や収穫状況次第では、再び価格が高騰する可能性も。
新米が去年の倍の値段。 pic.twitter.com/wkJQck6P70
— 紫蘭 (@bletilla87) August 20, 2025
概算金1.7倍と猛暑の影響が深刻!
JAによる高額な概算金だけでなく、2025年の新米価格上昇には“天候”も大きな影響を与えているようです。
特にこの夏の猛暑や水不足はコメの生育に深刻なダメージを与えているんです。
2025年新米を誰も買わなかったら・・・
— 長身ボッチスター (@black_coffee195) August 20, 2025
販売店・スーパーには備蓄米と2024年産米が溢れかえって値段も高価。
今年の新米は今回も海外に安値販売品として取り扱われるんでしょうね。
今こそ備蓄米放出の時☝️なのに・・・😢 pic.twitter.com/lt6Oue6JOl
猛暑・水不足による収穫量減少の懸念
今年の夏は全国的に猛暑日が続き加えて各地で深刻な水不足が起きています。
その影響で「高温障害」と呼ばれる異常現象が発生しておりコメの品質が落ちたり、粒が十分に育たなかったりするケースが増えているんですね。
専門家の折笠俊輔さんは「今年の新米の収穫量が減るのではないか」という市場の不安がすでに広がっていると指摘しています。
この“収穫量の不安”は市場心理を一気に冷やし、結果として価格高騰へとつながる傾向があるようです。
つまり価格は「供給量の見通し」でも大きく左右されるということですね。
令和6年産のコメは古米として残るのか?
新米の価格が上がる一方で「じゃあ去年のお米=古米は安くなるの?」と気になる人もいますよね。
たしかに令和6年産のお米が古米として市場に残る可能性はありますが、それも状況次第なんです。
専門家の大泉一貫さんによると「やっぱり“新米”のニーズは強く、古米があっても新米の価格は下がりにくい」とのことです。
つまり、多少市場に古米があっても消費者の多くは“新米の美味しさ”を求めるため、あまり価格競争が起こりにくいんですね。
一部では備蓄米や古米との混合ブレンドで価格を抑えた商品も出回っていますが、これらは品質や味に違いがあるため明確な差別化がされているのが現状です。
結果的に古米が流通していても、それが新米価格の大きな下落要因にはなりにくいと見られています。
新米の値段を心配してたけど、
— おかん (@maman1959) August 17, 2025
まさか?これほどとは
今年の新米5kg7800円も 異常な高値に業者も困惑 「備蓄米売り切れない」悲鳴も(テレビ朝日系(ANN)) https://t.co/e4CYph7300
消費者の声と家計への影響は?
生産者側が価格上昇を歓迎する一方で、消費者の立場では「ちょっと待って…」という声が増えているのが現実です。
新米が5kgで4000円を超えるという状況は、特に年金生活者や子育て世帯にとって深刻な問題です。もちろんそれ以外の一般の家庭にもかなり影響がでると思います。
高温障害がコメの品質に及ぼす影響とは?
猛暑が続くとお米の品質に直接的なダメージが出てきますね。
その代表的なものが「白未熟粒(しろみじゅくりゅう)」という現象です。
これはお米の粒の中が白く濁ってしまい、味も食感も落ちる状態のことなんです。
特に夜の気温が高いままだと稲がしっかりと休めず、栄養を蓄えきれなくなるんですね。
これにより本来なら高品質で流通できたはずのお米が“二等米”や“加工用米”として扱われることになり、出荷価格が下がってしまいます。
でもその一方で、品質の良いお米は逆に“希少価値”が高まり、より高値で販売されるという仕組みがあるんです。
つまり品質のバラつきが生まれることで、価格帯にも差が出てくるというわけですね。
スーパーでの価格動向と買い控え傾向
全国のスーパーでは、2025年の新米が9月中旬から本格的に販売開始される予定です。
その価格は5kgあたり税抜き3700円〜4000円ほど(税込だと4000円〜4300円前後)と見込まれています。
これは昨年よりも500円以上の値上がりになるとされており、売り場では「消費が落ち込むのでは」と懸念の声もあります。
実際に価格が高くなることで、消費者が買い控えをする“プチ米騒動”のような動きも起き始めています。
とくにブランド米などは価格のインパクトが大きく、日常的に購入していた家庭が「別の選択肢を探そうかな…」と感じる状況になってきているんですね。
実際の声「高すぎて買えない」「年金生活者には厳しい」
新米価格の上昇に対してSNSやニュースサイトのコメント欄には、さまざまなリアルな声が寄せられています。
「農家を守るのはわかるけど、消費者も守ってほしい」「5キロ4000円以上じゃもう買えない。年金生活者にとってはキツすぎる」「食費がじわじわ圧迫されて、他を削るしかない」
こうした声から見えてくるのは“応援したい気持ちはあるけれど、現実には手が出しづらい”というジレンマなんです。
また家族の多い世帯や、一人暮らしの若者たちの間でも「今後はパスタやパンに切り替えようかな…」という動きが見られるなど食生活自体の変化も起こりつつあります。
まさに“価格以上に生活全体に影響を及ぼす”状況になりつつあるんですよね。
このままではいわゆる「コメ離れ」がさらに加速してしまうかもしれません。
今後の価格動向と備える方法
ここまでで新米の価格が上がっている背景や、消費者のリアルな声を見てきました。
では「これからさらに上がるのか?」、「どう備えればいいのか?」が気になりますよね。
安く買うならいつ?買い時のタイミング
結論から言うと新米を安く買いたいなら「10月下旬〜11月」が狙い目です。
9月中旬から出始める新米は、収穫量や品質が見通せない“初物”として高値がつきがちですよね。
でも10月末ごろからは流通量が安定しはじめ、価格も少しずつ落ち着く傾向にあるようです。
さらにスーパーやネット通販では「早期予約特典」や「ふるさと納税」などで、実質的に割引価格で購入できるキャンペーンもあります。
購入する際は5kg単位ではなく10kgや20kgの“大容量パック”を選ぶことで、1kgあたりの価格を抑えることもできますよ。
備蓄米やブレンド米という選択肢
価格が高くて新米に手が出ないとき、注目されているのが「備蓄米」や「ブレンド米」です。
備蓄米は政府や自治体が万が一のために保管していたお米を市場に放出するもので、価格が安く設定されていることが多いです。
一方でブレンド米は古米や品質にばらつきのある米を組み合わせて作られており、スーパーでは「業務用米」や「お買い得米」として販売されています。
これらは味や食感に多少の違いはあるものの「とにかく安く米を確保したい!」という方には選択肢のひとつです。
さらに最近では玄米やもち麦などをブレンドして炊く“健康志向のミックスご飯”も人気。
味に変化がつくことで飽きずに楽しめる上、コストも抑えられるというメリットがあります。
でもこうした対応だけでは根本的な解決にはなりませんよね。

我が家ではもち麦や押し麦、玄米、雑穀米など色々なバージョンのミックスご飯を食べています。美味しくて健康的だと思います♪
政府・自治体の対策や支援策は?
新米価格の上昇が全国的な問題となっている中で、政府や自治体も対応を進めています。
まず注目されているのが備蓄米の放出による市場価格の調整です。
これは「米価が急騰しないよう、在庫分を市場に出すことでバランスをとる」という仕組みで、2025年も6月頃から実施されています。
また、いくつかの自治体では「ふるさと納税の返礼品としてお米を増量」したり、「低所得世帯への食料支援」として配布する動きも出てきています。
ただしこれらは一時的な対応に過ぎないため「長期的に価格を安定させる」ための施策としては、生産支援や農業従事者への補助金強化が今後の鍵となりそうです。
政府としても「農家も消費者も守る」中立的な立場での調整が求められているんですね。
まとめ
今回の記事では、2025年の新米価格がさらに上昇している理由とその影響について詳しく解説しました。以下に要点をまとめてみました。
- JAが提示する「概算金」が前年比1.7倍以上に引き上げられた
- 猛暑や水不足による収穫量の減少が価格上昇を後押し
- スーパーでは5kgあたり4000円超が当たり前に
- 農家は歓迎、一方で消費者からは「高すぎる」と嘆きの声も
- 買い控えや“コメ離れ”がじわじわ進行中
- 対策としては、備蓄米・ブレンド米・ふるさと納税などがおすすめ
- 買い時は10月下旬〜11月が狙い目
- 政府や自治体も価格調整や支援策に動き出している
このように新米価格の背景には複雑な事情がありますが、私たち消費者にも選べる工夫や備えはありますよね。
“安さ”だけでなく“おいしさ”や“地域の応援”という観点で、今年のお米選びを見直してみるのもいいかもしれませんね🍚
最後までご覧いただきありがとうございます。
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b776a1d.04626ccc.4b776a1e.1195f1e4/?me_id=1194822&item_id=10000347&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fjcrops%2Fcabinet%2F2-120.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b777171.9f00cfaf.4b777172.a9cb1df8/?me_id=1314045&item_id=10000140&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ff014583-higashikawa%2Fcabinet%2F06344090%2F10684010%2Fy-sku.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b77740b.c51c5d47.4b77740c.b6e420c4/?me_id=1397054&item_id=10017705&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbenefitshop%2Fcabinet%2Fmus08%2Fs5402-ydk-5062-4_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b776b01.c0dc81a4.4b776b02.7de2eb99/?me_id=1366602&item_id=10000450&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ff173860-hodatsushimizu%2Fcabinet%2Fyui2025%2F38601136_skua.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4b776fc2.c107749d.4b776fc3.a3771482/?me_id=1302867&item_id=10000069&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Ffuchigami%2Fcabinet%2Fmiruki%2Fr7-kmiru-smn-s10.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
コメント