2025年10月、日本初の女性首相が誕生するという歴史的な節目を前に、衝撃的な発言が飛び出しました。
BS朝日の討論番組でジャーナリストの田原総一朗氏が放った「死んでしまえ」という発言が、SNSを中心に大炎上。
登山家・野口健氏の批判をはじめ、テレビ番組の責任や言論の自由の線引きに関する議論が巻き起こっています。
この記事では、田原氏の発言の背景にある「高市早苗総裁との因縁」や、SNSでの反応、ジャーナリズムに問われる責任について、わかりやすく解説します。
ぜひ最後までご覧ください。
【発言】田原総一朗氏、高市総裁めぐる議論で野党議員に提案「死んでしまえと言えばいい」https://t.co/2zSZSBdzq7
— ライブドアニュース (@livedoornews) October 20, 2025
討論番組で、高市首相誕生を見越した議論中、田原氏は立憲・辻元清美氏と社民・福島瑞穂氏の主張を聞いたのち、冗談のように発言。福島氏は「それは絶対に…」と制止した。 pic.twitter.com/AXsgaQuMiR
「あんな奴は死んでしまえ」田原総一朗氏の暴言が物議に
テレビ番組中に飛び出した田原総一朗氏の「死んでしまえ」発言が、ネット上で大炎上しています。
問題の発言は、BS朝日「激論!クロスファイア」での高市早苗総裁をめぐる議論中に飛び出しました。
高市総裁に関する議論がヒートアップする中、田原氏は「反対すればいいじゃん」「あんな奴は死んでしまえと言えばいい」と発言。
スタジオにいた福島瑞穂氏や辻元清美氏も思わず「それはダメ」と制止し、場の空気は一変しました。
過激な発言に、出演者や視聴者が驚きを隠せなかったようです。
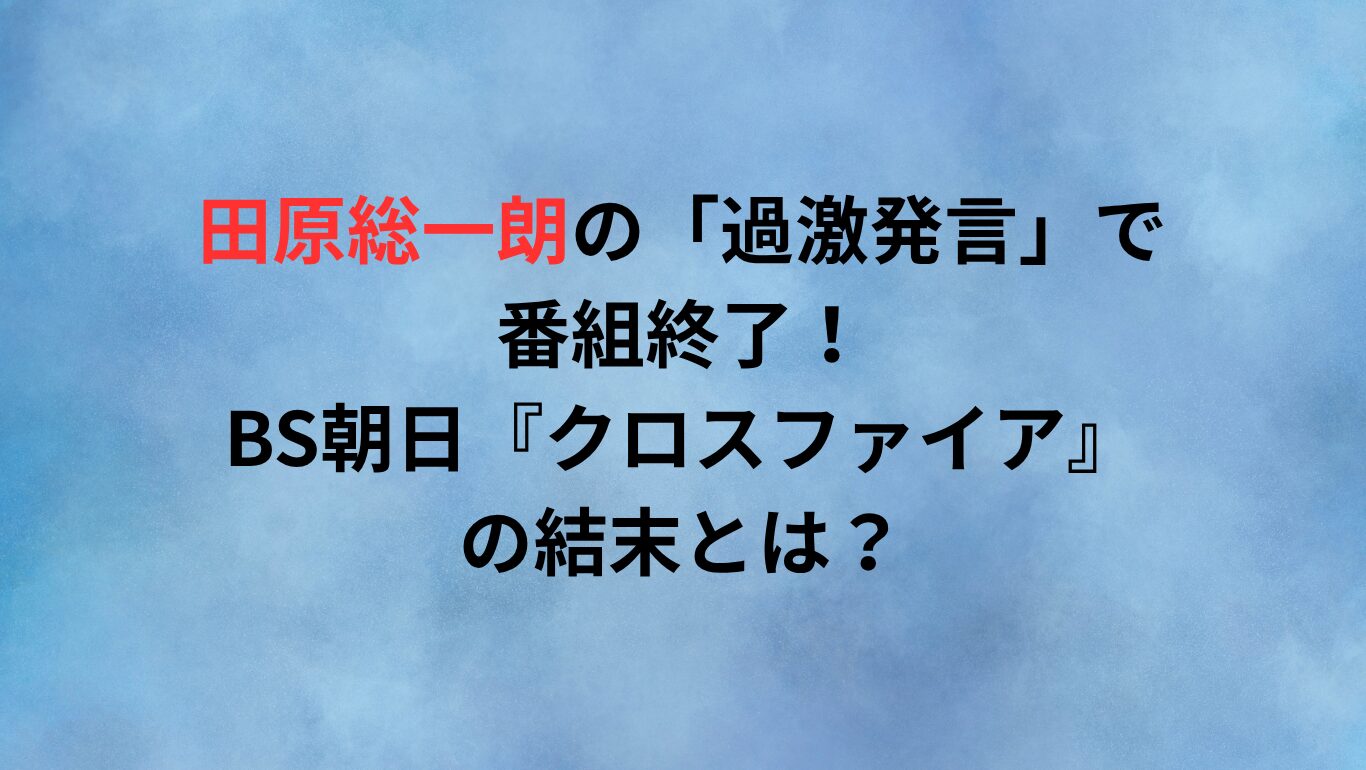
番組で飛び出した問題発言の詳細
田原総一朗氏の発言は、「高市氏に反対するなら、あんな奴は死んでしまえと言えばいい」というものでした。
発言の瞬間、福島氏はすかさず「それは絶対に……」と遮り、辻元氏も「また高市さんと揉めるよ」と指摘しました。
田原氏は笑みを浮かべながら話していましたが、言葉の重さを軽視できる状況ではなかったようです。
そのまま番組はCMに入り、この話題には触れられませんでした。
しかし、放送後すぐにSNS上では怒りの声が広がりました。
テレビという公共の場で、命に関わるような言葉を発することへの批判は当然でしょう。
この発言が視聴者の信頼を大きく揺るがしたのは間違いありません。
高市総裁との確執とは?電波停止発言からの因縁
田原氏が高市総裁に対して過去から強い対立姿勢を示していたことをご存知でしょうか?
発言の背景には、2016年の「電波停止」発言にまつわる因縁があると考えられています。
2016年の「電波停止」発言とは
当時総務相だった高市氏は、放送局が政治的公平性を欠いた場合には「電波停止もあり得る」と国会で答弁。
この発言は、報道の自由を脅かすものとして全国的に大きな議論を呼びました。
これに対し、田原総一朗氏を含むジャーナリストたちは抗議声明を発表しました。
田原氏はその後も「報道に口を出す政治家」として高市氏を厳しく批判し続けています。
今回の発言も、この延長線上にあると言えるでしょう。
田原氏が高市氏を敵視する理由
田原氏は、自身が長年メディアの第一線で活動してきた誇りを持っています。
そんな田原氏にとって、高市氏の「電波停止」発言は、まさに“報道の敵”と映ったのでしょう。
今回の「死んでしまえ」発言には、個人的な感情や過去の対立が滲んでいるように見えます。
しかし、それでも「死ね」などの言葉が許されるわけではありません。
多くの視聴者は、その点に強い違和感を持ったのではないでしょうか。
SNSや著名人からも批判殺到!炎上の広がり
田原氏の発言はすぐさまSNS上で拡散され、非難の声が殺到しました。
特に、著名人の発言が炎上に拍車をかけました。
野口健氏の「テロ容認」批判が話題に
登山家の野口健氏は、X(旧Twitter)にて「この発言はテロを容認しているようだ」と強く批判。
「人に死ねというのは、冗談でも許されない」と断言し、メディアの責任を問いました。
この投稿には多くの共感が集まり、「田原氏はもう引退すべきでは?」という声が噴出しました。
一部のネットユーザーからは「認知症では?」といった言葉も出ており、発言の深刻さが伝わってきます。
SNS上の声「老害」「BPO案件」の嵐
SNSでは「BPOに通報した」「これはテレビ局の責任問題」といった意見も多く見られました。
中には「超老害ここに極まれり」といった厳しい言葉も。
一方で「田原さんは好きだったのに残念」と悲しむ声もあり、かつての名司会者としての評価とのギャップに戸惑う人も多いようです。
ネットの声は、田原氏個人への批判にとどまらず、テレビ局や番組全体への不信感へと広がっています。
田原総一朗氏「(高市さんに)死んでしまえと言えばいい」 テレビで発言し物議…福島瑞穂氏もドン引き : はちま起稿 https://t.co/drTNEJM7LA
— 超がりちゃん (@chougarichan) October 20, 2025
コンプラも分からない老害や😁
91歳ジャーナリストに問われる言論の責任とは
問題の本質は、年齢や過去の実績ではなく「公共の電波で発言する責任」です。
田原氏が91歳であろうと、テレビ出演者である以上は発言の責任が伴います。
公共の電波での発言に対するルールと倫理
放送法やBPO(放送倫理・番組向上機構)は、公共性を持つ放送の内容についてガイドラインを定めています。
その中でも、命に関わる言葉や暴力的な表現は、原則として許されません。
田原氏の発言は、これに反していると多くの人が感じたからこそ、ここまでの炎上を招いたのです。
番組制作者も、こうした人物を出演させ続ける責任を問われるべき段階に来ているのかもしれません。
言論の自由と暴言の境界線とは?
言論の自由は民主主義の根幹ですが、それは他人の尊厳を傷つける権利ではありません。
今回のケースは「自由」の名のもとに暴言が許されるべきでないことを示す、象徴的な出来事でした。
え?これ高市総裁に向けて言ったの!?
— あーぁ (@sxzBST) October 20, 2025
言っていいことと悪いことの判断もつかないぐらい年老いてしまったんだね。
二度と出て来るな💢
「死んでしまえと言えばいい」田原総一朗氏 “反高市”の野党への衝撃提案にスタジオ騒然…SNSでも「BPO案件」と疑問の声(女性自身)https://t.co/gc75hkgZFF
まとめ
今回の記事ではこんなことを書きました。以下に要点をまとめます。
- 田原総一朗氏が「死んでしまえ」とテレビ番組で発言し、物議を醸した
- 発言の背景には2016年の「電波停止」発言をめぐる高市総裁との確執がある
- 登山家・野口健氏をはじめ、SNS上でも批判が殺到している
- BPO案件との声や「老害」「認知症では?」といった厳しい意見も多い
- 公共の電波における発言の責任や、言論の自由の線引きが改めて問われている
SNS時代の今、テレビでのひと言が一気に拡散し、社会的影響を与えることは避けられません。
だからこそ、どんな立場であれ、発言には責任が伴うということを改めて考えさせられる出来事でした。
さすがに言っていいことと悪いことの区別がつかない方に、TV出演させるのはおかしいと思います。これからはこの方を出さないでいただきたいですね。
最後までご覧いただきありがとうございます。
コメント